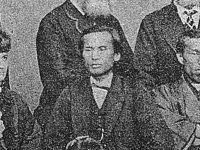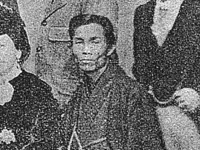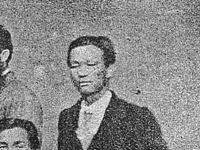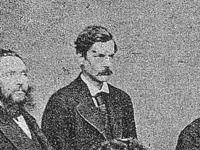啄木鳥Top
啄木鳥Top |
| <引用資料> 「外国人と大隈」について 慶應義塾大学 高橋信一 |
|---|
|
<引用資料> 「外国人と大隈」について 慶應義塾大学 高橋信一  この写真が上野彦馬のスタジオで撮影されたことは手前の石畳を剥ぎ取った跡の形からわかっていたが、大隈会館や早稲田大学でもオリジナルがなく、詳細が不明だった。大正11年2月に大隈重信が亡くなった時に雑誌「実業之日本」の「大隈侯哀悼号」が出て、その中でこの大隈夫妻を囲んだ外国人たちの写真が掲載された。キャプションには「明治初年頃の外賓と外交官大隈侯」とあるが、大隈は明治元年以降ほとんど長崎に行っていないので、どこかに間違いがある。これは実は以下のような写真であることを森重和雄氏との情報交換の中で発見した。 明治4年5月に創刊された「新聞雑誌」の明治5年11月号に「10月29日に灯台及び電信視察のため大隈侯等が巡視船で大阪・神戸・長崎に向け出航した」とある(「新聞集成 明治編年史」。記事の中に、乗り込んだ人員として大隈重信、山尾庸三、佐野常民、石丸安世の他に杉浦譲、石井忠亮、佐藤興三、フレッシャー、カーギル、ボイルとアーネスト・サトウの名前がある。また大隈と山尾の伝記には10月28日に長崎出張を命じられたことが記されている。当時、日本中に灯台を建設する工事と、長崎−東京間の電信線ケーブルの敷設が急ピッチで行われていた。また、鉄道の敷設やその準備のための用地探査も行われていた。大隈らはそれらの状況視察に出向いた訳である。 そこで、この灯台巡回に同行したサトウの日記をまとめた「図説アーネスト・サトウ 幕末維新のイギリス外交官」に載っていた「灯台巡回日誌」を「大隈文書」で見てみた。二種類の日誌を総合すると以下のようになる。 明治5年10月29日 横浜港出航 11月 5日 大阪で杉浦譲下船、早や馬で帰京 11月12日 長崎港着 11月13日 伊王島灯台、小菅造船所巡視 11月14日 石炭積み込みのために巡視休み 11月15日 朝10時大浦電信局視察 12時30分 長崎港出船 11月16日 門司で投錨 11月21日 神戸碇泊 11月28日 午後3時 横浜港帰着 また、「遠い崖 アーネスト・サトウ日記抄」には大隈と山尾が夫人同伴で行ったと書かれていた。つまり、大隈たちは明治5年の11月12〜15日の4日間だけ長崎に滞在していたのだ。11月14日の「巡廻日誌」には「この日、記すべき事なし」と書いてあり、仕事は休みとなったので、上野彦馬のところに行って写真を撮った。「サトウの日記」には、その日の夕方に明治天皇が巡幸の途中で泊まった料亭で会食したと書かれている。岩倉らの米欧回覧の留守を守る超多忙の大隈のつかの間の休息だった。と云うわけで、この写真は明治5年11月14日(土曜日)に上野彦馬の写場で撮影されたものである。当日の長崎の天気は晴れで絶好の写真日和だった。杉浦譲は途中大阪で降りたので、長崎に行っていない。外人はサトウ、ボイル、カーギル、フレッシャーの他ジョージというのが乗船しているので、そのだれかだが、写っている外人の男性は6人。最初から長崎にいた人物がいるのかもしれない。 次に写っている人物の同定だが、大隈夫妻の左隣りが山尾夫妻だということは山尾の孫の山尾信一氏に確認してもらった。「写真の開祖 上野彦馬」には「丸山の芸者」と名づけられた女性二名の立ち姿の写真があるが、顔かたち・服装がまったく同じで、本当は大隈と山尾の夫人たちの写真であり、この時に撮られたことが判明した。 佐野常民は「東京国立博物館所蔵幕末明治期写真」の写真と比べると中列右端に座っている人物。この後、佐野はウィーン万博事務副総裁として明治6年2月にウィーンに出かけた。大隈が総裁だが、岩倉使節団で政府の要人が払底しているので、出かけていない。とうとう大隈は外遊を一度もしなかった。 石丸安世は「中牟田倉之助伝」の写真を参考にして後列右端の人物、アーネスト・サトウは上の「図説サトウ」の本の写真からして後列左から二人目、ボイルは後列のど真ん中の人物であることが、「鉄道人物録」からわかった。 一番左に座っている人物は石井忠亮だと思われる。 残った外人については今後の調査次第である。尚、当時鹿児島にイギリス人の医師ウィリアム・ウィリスがいたが、長崎には出かけていないことが確認出来ている。(平成18年4月30日) |
 kitu888tuki@yahoo.co.jp |