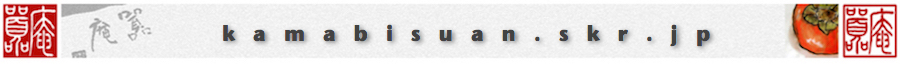
囂庵ホームページ


日記で観る戊辰・己巳の箱館
酒井孫八郎日記
plus
石井勇次郎戊辰戦争見聞略記
plus
小野権之丞日記(明治元戊辰年日記および明治二己巳年日記
plus
箱館戦争と大野藩
お断りの注
庵主は自分自身のために、それぞれの原文の姿をのこしつつ、読みやすく大胆に要約意訳のアレンジを試みております。
したがって「史料」として扱うには、若干いやいや相当よろしくありません。
また、オリジナルdataにも、誤記などが多く、それにもまして、庵主の誤訳誤解も多くあるやも知れません。
この件、しっかりおことわり申しあげます。もし、これにご不満のご人は、ご自分で原文をお読みお確かめ下さい。
したがって「史料」として扱うには、若干いやいや相当よろしくありません。
また、オリジナルdataにも、誤記などが多く、それにもまして、庵主の誤訳誤解も多くあるやも知れません。
この件、しっかりおことわり申しあげます。もし、これにご不満のご人は、ご自分で原文をお読みお確かめ下さい。
底本は
維新日乗纂輯四より 酒井孫八郎日記 慶応四戊辰歳正月元旦〜明治二年八月二十七日
新人物往来社刊 新選組史料集より 石井勇次郎 戊辰戦争見聞略記 慶応二(三)丁卯六月十四日〜明治二年十一月二十三日
維新日乗纂輯四より 小野権之丞 明治元戊辰年日記(六月十八日〜十一月八日)および明治二己巳年日記(二月二十三日〜十二月晦日)
小野権之丞 会津藩公用人 のち榎本海軍に身を投じ、五稜郭の箱館病院事務長として高松凌雲と共に敵味方の区別無く負傷者の治療に当たる。
箱館戦争と大野藩(大正七年高島文庫刊)より *ただし日記でないため、日時の記述がある部分のみを記す。
| 1868年 | 明治元年九月 小 | |
| 10.30 | 十五 | 石井略記(略) 大野藩 九月十五日仙台藩帰順し、 |
| 10.31 | 十六 | 石井略記(略) |
| 11.1 | 十七 | 石井略記(略) |
| 11.2 | 十八 | 石井略記(略) |
| 11.3 | 十九 | 石井略記(略) |
| 11.4 | 二十 | 石井略記(略) |
| 11.5 | 二十一 | 石井略記(略) |
| 11.6 | 二十二 | 石井略記(略) 大野藩 二十二日会津城陥り、 |
| 11.7 | 二十三 | 石井略記(略) 大野藩 翌日(二十三日)庄内降りて戦局収り。 |
| 11.8 | 二十四 | 石井略記(略) |
| 11.9 | 二十五 | 石井略記(略) 大野藩 大野藩百七十人の一隊が征途に上る九月二十五日は来りぬ。・・・・ |
| 11.10 | 二十六 | 石井略記(略) 大野藩 翌二十六日 晴。・・・ |
| 11.11 | 二十七 | 石井略記(略) 大野藩 未の刻半(3時)敦賀着 |
| 11.12 | 二十八 | 石井略記(略) |
| 11.13 | 二十九 | 石井略記(略) |
| 1868年 | 明治元年十月 大 | |
| 11.14 | 朔日 | 石井略記(略) 大野藩 25252 |
| 11.15 | 二 | 石井略記(略) |
| 11.16 | 三 | 石井略記(略) 大野藩 [榎本軍の動向] 大野藩士の敦賀出帆に前つ五日、すなわち十月三日をもって艦船を修理處より東名濱に集め食料薪水を積み込み、 |
| 11.17 | 四 | 石井略記(略) |
| 11.18 | 五 | 石井略記(略) |
| 11.19 | 六 | 石井略記(略) 大野藩 十月六日晴。四時、敦賀出帆。(チャーター艦モナ) しかし、七時、積荷の積載過多のため兵士の横たわるスペースも無く大もめ、結局敦賀に戻り調整することになる。 |
| 11.20 | 七 | 石井略記(略) 大野藩 敦賀港にもどり、一旦積荷をおろし、積荷の調整。 |
| 11.21 | 八 | 石井略記(略) 大野藩 晴。午後曇。早朝より積荷開始。三時、敦賀港を出帆。 |
| 11.22 | 九 | 石井略記(略) 大野藩 翌日 終日風時々雹。能登沖。 [榎本軍の動向] 大野藩開帆の一日後すなわち、九日には折の漬(宮城県牡鹿郡荻ノ濱村)に転じ、 |
| 11.23 | 十 | 石井略記(略) 大野藩 翌翌日 大風雪。申刻越後村上領粟島に仮泊。 [榎本軍の動向] その翌朝、榎本大鳥等の諸師、其の日回航の旗艦開陽に乗り込み、 |
| 11.24 | 十一 | 石井略記(略) |
| 11.25 | 十二 | 石井略記(略) 大野藩 3333 [榎本軍の動向] 十二日開帆、前後して、 |
| 11.26 | 十三 | 石井略記(略) 大野藩 十三日 風濤のため男鹿半島舟川湊に避難。 |
| 11.27 | 十四 | 石井略記(略) |
| 11.28 | 十五 | 石井略記(略) |
| 11.29 | 十六 | 石井略記(略) |
| 11.30 | 十七 | 石井略記(略) |
| 12.1 | 十八 | 石井略記(略) |
| 12.2 | 十九 | 石井略記(略) 大野藩 十九日払暁 野田監督よりの秋田引払い乗艦出帆の報に接し、直ちに兵器、緊用物品の積み込みに従事し、二時兵士輜重の搭載を了え、下宿の支払いをも為し、直ちに開帆、更に蝦夷地を指しぬ。 [男鹿の舟川をやっと出帆] 艦は北へ北へと進み、 |
| 12.3 | 二十 | 石井略記(略) 大野藩 二十日晴れ 四時頃には、松前の大島小島と松前地方を左舷に右折し、津軽海峡の濤にも阻まれず、未刻巴港すなわち箱館港に着し、兵士は実行寺、幹部は大町二丁目の山手にある大野屋に止宿する事とし、荷物の揚陸は明朝と定め、半ヶ月の困苦を休養せんと期せしに、豈図らんや東軍既に噴火湾方面より上陸し砲火相見ゆるの機熟し居らむとは。 [箱館に着いたはいいが・・・さあ大変] 十月二十日 大野藩兵箱館へ着港するやいなや、野田試補より左の通達を発せしかば、 旧幕脱艦数艘近海へ出没、勢甚切迫実に異変も難計候に付き、兵隊へも右の趣意御申し通し置有之、
中村隊長はとりあえず三監察を随えて野田の旅館(山ノ上元本陣税館と相対す)に赴き、福山藩隊長等と会い、同軍議のうえ、明旦より大野藩は谷地頭、福山藩は尻沢辺へ斥候として一小隊宛差遣。福山砲隊は弁天砲台を守備し、且つ夜間に荷揚げをなす事を船長に談じ、旅館には異変報告のため両藩より二斥候を遣わし置くことを決議し、軍務官の地図に就きて間道地形を調査し、在住弘前一小隊宛茅部峠へ斥候として進軍せし事抔(など)聴き取り帰宿。小松雄次郎、浅山金八を斥候となし軍務官に派遣し、薄暮軍務官より着港慰労として酒一樽肴二尾を中村隊長に送り来たりしを幹部に分配したりき。後刻隊長の者は軍務官へ罷り出るべく云々 其藩兵隊夫卒追々朝廷御用被召仕候者え為御慰労別紙目録之通被下賜候條其旨通達可被在候 以上 夜十時ごろ左の回状を参謀より発し、且つ覚え書きを在留外人に致しぬ。
十月二十日 箱館出張 軍務官 会計 中村雅之進 殿 ○廻章
半夜鷲木村へ出張の荒井信五郎より左の警報達し、冶装土足の儘仮眠せし全軍を驚動したりき。旧幕艦七艘当時南部領宮古湊え碇泊之處当地へ襲来候哉に相聞重畳不穏形勢に付明日御軍議之上海岸受持場をも可被命候共差当り今晩にも異変有之候はば直に及御報知候間其節は南部陣屋敷跡え急速兵隊被及御繰出候様当県知府事殿より御指図候條其旨一統え御布告臨時出張有之様御覚悟肝要に候事 十月二十日八字 野田大蔵 福山 大野 隊長御中 ○覚 一、戦器其外石炭食糧薪水に至る迄我朝廷之土地より出産せる物品は塵芥と雖も與ふるを許さず 一、重立たる者は勿論銃卒水夫人足等に至る迄一賊たりとも我朝廷の土を踏を許さず 一、総て海岸より一里内へ乗入は端船と雖も我より砲撃すべし何となれば賊船たるは明白なる上揚陸を許さざる以てなり 一、口に謝罪を唱え甘言を吐くと雖も決て不可聴何となれば従来の処置不穏且別に我に於て見込あるを以てなり 右四ヶ條之内は平穏に進退し懇切に乞うと雖も一言片辞を聴を不許 辰 十月
徳川海軍 開陽丸 端船十五艘 回天丸 端船十五艘 蟠龍丸 端船五艘 神速丸 端船三艘 軍務官は直ちに之を各隊に急告し、明曉は谷地頭尻沢辺への派兵をも達せしかば、大野藩は即刻(子過刻ぎ)久保木弾薬方を早船にてモナ艦に遣わし弾薬その他の揚陸に着手せしぬ。長鯨丸 端船十五艘 大江丸 端船十艘 回春丸 端船五艘 鳳凰丸 端船五艘 右船之内一艘(旗艦開陽十九日着)当村懸より夜五時半頃襲来村会所え三十人(朝廷への嘆願書を持った人見本多等)計上陸いたし明朝五六百人程上陸致候間湯宿手配致候様申聞候、薪五百敷用立可申旨申聞候(一敷は長さ一尺四寸の薪を巾五尺高六尺に積しを云い現に北海道常用語たり) |
| 12.4 | 二十一 | 石井略記 注:以下石井勇次郎の戊辰戦争石井略記 緑文字表記
大野藩 翌二十一日 嵐。払暁中村隊長は福山藩と同道不時集合地たる南部陣屋を視察し、会計方をして軍用金を諸士以上へ三両同以下へ二両軽卒へ一両二分中間へ一両宛分たしめ、昨夜半より着手、十時頃(巳刻)迄に揚陸せし弾薬輜重は悉く大野屋へ積み込ましめ、正午堀の第一小隊を谷地頭に赴かしめ、野田試補・岡田福山隊長と共に五稜郭に赴き清水谷知府事に謁し軍議を重ね十時後に帰宿したりき。この日以後出征兵士の給養は政府より支給さるる事となれり。同廿一日、八艦先後ありといえども、共に蝦夷地鷲ノ木村に達す。直ちに上陸して先鋒するも在り。我が隊は翌朝上陸す。然るに大雪漫々、かつ山深し。仰ぎ見ては駒ヶ岳有り。高さ天に接す。この山に相原周防守の城跡あり。東方を望むに、遙か海上数十里を隔て蝦夷不二と称する山を見る。そのかたち駿の士峯に異ならず。・・・・(中略) 箱館にある官軍、我が数艦この地に来るを知り、諸口守兵を出して固めしむ。故に我が軍も速やかに議し箱館に住す各国公使に潜に使節を送り、我蝦夷地に来たり恢復を計らんと欲するの状、審に明文をもって布告す公使託す。使節に行く者探索方幕人小柴長之介、加藤昇太郎也。 直に勢を揃ひ函館を差て諸道を襲ふ。河汲口を進む者(間道なり)額兵隊四百余人を率る者、仙藩星仁太郎也。陸軍隊三百余人を率する者春日左工門也。教師仏人ブヘー也。此軍土方君を以て総督と為して進む。 又本道を進む者、新選組六十五人を率る者安富才助也()同附属士官隊四十人を率る者川添誠之丞也、伝習士官隊三小隊を率る者滝川充太郎也、同歩兵三百余人を率る者本多幸七郎、遊撃隊に小隊を率る者人見勝太郎也、工兵隊(土木兵なり)に十人を率る者吉沢勇四郎也、教師仏人フリネマルラン也。 此軍大鳥圭介君を以て総督と為て進也。 鷲ノ木の本営を守、且諸方の援兵と為す者、彰義隊に百八十人を率る者池田大隅、渋沢誠一郎也、衝鋒隊(歩兵)七百人を率る者古屋作左工門也、一連隊(歩兵)三百人を率る者松岡四郎次郎也、各守を定む。 大鳥の軍、予隊は先鋒と成、余は悉く続て発し此日森村に至る。諸口へ番兵を置泊す。 |
| 12.5 | 二十二 | 石井略記記載なし |
| 12.6 | 二十三 | 石井略記同廿三日、暁天に発して峠下村(鷲ノ木をへだつ九里、この峠は嶮にして箱館を守る肝要の地なり。)に至りて是に泊す。是に於いて予新選組のきょう導役を命ぜらる。前日是に於いて遊撃隊、伝習士官、歩兵右三隊にて三百余人を以て峠に戦い、敵嶮を守るといえども、弱にしてたちまち散乱し是を得る。敵は津軽備の福山越前大野という。 予隊、是に来るが故に又軍議し、軍を分かち二となし、一は附属士官及び伝習官、歩兵右三隊をもって大野村方面(箱館へ出る本道なり)に向かう。一つは我隊先鋒となり、遊撃隊、工兵隊(土木の兵)、百十数をもって七飯村方面に向かう。 |
| 12.7 | 二十四 | 石井略記同廿四日、二軍共発し、予隊七重村に進むと雖敵無し。当村を出れは浩々たる野を隔つ一里余にして、野の側に大川と称する村あり。是に敵大軍屯在すと言。直に是を襲ふと決議せんとす。予謂曰、
小野日記 注:以下 会津藩士 小野権之丞日記(明治戊辰年日記) 小豆色文字表記 敵は要地に胸壁を築て待つ。今我よく進み戦んと欲すと雖、斯大雪漫々、已五尺に至る。且被れ守る処の八方平野にして、我拠る所の要地更に無し。然るに此少兵を以て進戦ひは我利を得る難し、又人野村方面も(七飯村の右側にしてかつ一里眼下に見渡なり)戦たけなわにして未だ勝敗分たざるに、我兵拠処の地も無く先て此少兵を以て戦ひ必勝の策ありや。此口若し敗すれは、大野村方面の敵勢を増すに至りては諸隊に何の面目あらん、是人事ならんか故に、暫く大野の形勢を見、危ければ援けて共に進まんと欲するは何かん。 諸士然りと為し遂に予が意に決す、速に七重村要地諸々に胸壁を築て暫く守るに、第十字頃より風雪烈布起り寸暇も止む無し。雪烟の如くにして空上に漲り飛ふ、五歩を隔てば容貌見へず。寒気甚敷、銃を携るに手氷の如にして携ふ能ず。兵大に困す。予是を見るに忍ずして兵補はんと、八方尽力して酒を得んと欲すれども、固より辺土なれは更に無し。止を得す野菜を得て是を焚て食せしして一時の寒気を凌く。然るに第二字頃、敵降雪に乗し津軽藩の兵先鋒して、備の福山藩、松前藩、越前大野藩、薩長両藩、函館兵(元幕にしてこの地警護に来たり遂に官兵となる)合て凡弐大隊余と見ゆ、是を以襲来す。我兵百十数人を以て直に散して防がしむ。 山手を守る者新選組半小隊と遊撃隊一小隊也。野中に守る者、又右同隊一小隊也。 本道を守る者、予藩拾七人也。敵は野の草むらに兵を散伏して進み撃つ。我軍に氏家或は樹木に拠り兵を散伏して烈戦寸暇も止む無し。 然るに我藩守る処の本道、兵少なるを知り敵直に大兵を以て進み来つて戦ふ。我藩拾七人、西奔東に進み防くと雖、右を防かんとすれは左に迫り、是を防かんとすれは彼れに迫る。況や拾数人を以数百に当るをや、遂に敵せすして二、三町引揚る。途にして岡村亀太郎傷して倒る。予是を負て退かんとすれとも走る能す、故に敵兵近く進み来て予を狙い撃つ。殆と危と雖、天幸にして遂に命を全ふして是を助け来り。外人をして病院に送らして、速に兵をまとめーつの人家に籠もり、しきりに防戦すと雖、敵は機に乗じていよいよ迫るに、我弾薬已に尽き進退是に極る。 故に予十七人と議て曰、 今我藩守る処の此の目敗すれは、則桑の汚名を促すあに生て帰らんやと言。 皆死を決し大に奮発し直に刀を抜て敵軍切込み大に戦ふ。彼れを忽ち三、四人を切倒す、共勢ひ破竹の如し。又横道より我遊撃隊十人程進み来り援く。是を見るや敵大に恐伏し皆忽散乱して四方に走る。我軍此機を失はす凱歌を作り村の出口迄尾撃す。然るに山手の我軍此勢ひを見て、一時に山上より踊り下つて又敵を破る。敵散乱して皆五稜郭の方へ逃走る。我軍合して是を尾撃せんとす。予思らく是襲ふ可きの場にあらす、暫く止まれと雖、隊士奮て聞す故に、予走て軍目佐久間貞次に謂て曰、 此役我軍急に進撃する場合にあらす、君走り行て是を止め玉ひそ。 佐久間士奮然して曰、此機に乗し五稜郭迄も追はずんば有る可らざる也。 予諌て曰、君の雄気亦感す然と雖、再ひ之を思慮有可し。敵軍は固り我に十倍せり。今幸にしてー勝を得ると雖、大野邑戦ひや我後に在て未だ酣(たけなわ)也。故に横撃して之を援け是の形勢に依て其に進退す可し。今我兵勝に誇り後策及援兵、且弾薬も無く、只此少兵を以先浩々たる野地を追ひ少兵なるを顕さは、敵我軍を侮り返襲せんも量る可がらす。此時に当ては再ひ勝を得る難し。若し敗すれば此方面のみならず、他の方面の敵勢を増す。其時は諸隊に対し何の面目あらん。実是薄氷を踏が如しと言可策ならんか。故に大野村を援け機に依て策を立、弾薬を乞ひ然して後に襲はんと欲には、何かん君能是を思慮あらまほし。
佐久間姓尤然りと、直に走て令を下し止めしして亦七重村胸壁に揚け、諸口へ番兵を出して兵を休ましめ、弾薬を乞て大野村を援くるの策を議す。此役、我隊に戦死する者、唐津藩三好胖君(公の御二男なり)、同小久保清吉也。傷して後に死する者、桑藩竹内武雄也。傷者、唐津藩山口文次郎、西脇源六郎、天野十郎、明石覚四郎、我藩には森弥一左に門、岡村亀太郎、薄手は内山栄八、水谷藤七、金子庄兵衛、隊の歩兵善八也。亦大野村方面も戦利在て、敵村々人家を放火し有川駅の方へ敗走す。亦七重邑に戦也。敵の傷者を生捕る。備の福山藩十四人、長州の士一人也(是を我函館に引連病院高龍に入れ手厚く療治し皆全快するに及て後三月十日船に乗せ青森に送る希れなる扱ひ後世恥るなし)。 ・・・鷲の木へ着。 此夜、同藩之面々(会津藩の面面)出張相成候處、私義、病院懸可相勤旨榎本氏申聞に付、相辞し、出張之儀申立候得共、差閊(つかえ)候儀にて、存意不相叶。 三宅大學一同相勤居候。 函館100年 二十四日夜半 清水谷知府事らは五稜郭を出て箱館市内に移る。 |
| 12.8 | 二十五 | 石井略記 同廿五日、大野村方面より伝習歩兵附属士官隊応援として三小隊七重村に来り我隊に及。遊撃工兵苦戦の疲労を養はんか為に来る故に、代て我隊は大野村鎮撫として行き、暫く止て疲を養ふ。
小野日記記述なし此日直に両道共に進みて五稜郭を襲ふ。七重村の兵は河汲口の間道より進む。土方君は一軍を率ひ本道より進み河汲嶺にて戦ひ、忽破て五稜郭を襲ふ。七重村の兵も進途にして合し共二五稜郭を奪ふ。 敵は函館に走り戦かはすして是を得る。是に依て我本営と為す。後、是郭を見るに曾て(かつて)魯国人の縄墨を以て築く一郭の塁也。其形ち菱の如く、故に名付く。平地と雖要害の郭也。回は堤して高さ数丈有、周囲八町余、外は堀して水蒼々たり。菱の如く角に巨砲八十斤、廿四斤を備ひ郭外の八方は平野の如し。堅なるを以て陸戦にて破る能す。唯憂所、海近し故に海軍より放発するを憂る而已(のみ)也。 于時(ときに)海軍は回天艦を先鋒として回陽艦共に鷲の木を発し函館に来り直に上陸す。敵の総督清水谷卿を始め諸勢外国艦に乗し、津軽領青森に走る、依て回天艦直に是を襲ふ。誤て浅瀬に乗り上け進退叶はす、少くして走ると雖隔つ遠し。遂に追撃能すして帰帆して港に入、遺憾也。 亦戦はすして函館を得、彼れか積所の器械に及弾薬兵糧を奪多し。翌暁天、秋田の艦高尾丸、此条を知らすして入港す。回天是を見、直に舵を転し進て敵艦に乗掛談判して、遂に我艦と為す。乗組の人悉く降伏す。艦将は永山友右エ門と言。降り時阿州の臣と言、其実は薩人也。後船に乗せ皆青森に帰送後、回天独り青森に行上陸すと雖敵する者なし。市人に説論し仁義の士たるを示て衆人の心を安んせしめて帰港す。回天数々功を為す、実に称す可き也。 函館100年 二十五日 清水谷知府事らは青森へ逃げる。 |
| 12.9 | 二十六 | 石井略記記述なし 小野日記同断
函館100年
二十六日 榎本旧幕軍五稜郭を無血占領。
|
| 12.10 | 二十七 | 石井略記記述なし
小野日記 廿七日 桑名侯徳山侯山中侯後上陸。榎本氏より病院の義管轄被願。函館100年 二十七日 榎本旧幕軍、箱館に入港した秋田藩艦「高雄」を捕らえ、旧幕艦とする。 |
| 12.11 | 二十八 | 石井略記記述なし 小野日記同断 |
| 12.12 | 二十九 | 石井略記 同廿九日、我隊大野村を発し函館に至り市中取締を命せらる、一本木の関門を守る。
小野日記記述なし 我越地に於て傷して未た癒さるを押て歩し、且寒気甚しきか故へに大に譴(とが)め困と雖、ここに於て漸く平癒す。 [石井君、函館のにぎわいにビックリ] 我函館表面見に、曾て聞処に勝る。前面は港して碇泊す、外に方は悉く海して北の方少く陸に続く而已実に島の如くの地也。南方を仰て見れは市中の側に臥牛山あり。高さ天に接す。其麓よりして民家あり、其数一万軒と言。各国公使の館、及奥羽諸侯の陣屋数多あり。市中至て繁華也。側定芝居あり(東京両国などの芝居よりは遼か勝れり)。又両郭内と称して妓楼二ヶ所あり。一を山の上常盤町と称し楼二拾五軒、側り各国遊楼あり作り悉く夷風也。又引手と称して登楼の導を為す者二十五軒あり(家は悉く料理屋也)。一ッを築島と称し、又楼二拾二軒あり(是は新郭内と称して常盤町より一段下る也)。二ッ出入口に門を設け是を称て大門と言。又見番屋と称する者あり、芸妓は是に群集を為し客の招を待つ。妓婦は美を尽し内に連つて客を招ふ。楼中或舞、或謡て愉快を尽し昼夜三味太鼓の音、暇も止無し。又芸妓は客の招に応し音器を携ひ裾を飄て行あり。夫是を見に歩する者、毎夜群集を為す、実に東郭内の遺風あり。函館の繁華なる事衆の眼を驚す也。 我隊は函館の守を命せらる。 |
| 12.13 | 三十 | 石井略記記述なし 小野日記同断 |
| 1868年 | 明治元年十一月 大 | |
| 12.14 | 朔日 | 石井略記 十一月朔日、松前方面に向ふ者彰義隊弐百八十人を率る者渋沢成一郎也、額兵隊四百余人を率る者星仁太郎也、陸軍歩兵二百五十人を率る春日左エ門也、同士官五十人を率る者朝倉隼之進也、工兵隊を率る者小菅辰之介也、此軍土方君を以て総督と為し、五稜郭を発し尻打峠に至り宿陣す。然るに敵、松前藩福島駅より潜に舟に乗し来て夜襲す。少く戦ひ破て尾撃し、同二日福島を進撃す。
函館100年
一日 松前に向かった土方隊は知内で奇襲を仕掛けた松前藩兵を敗走させる。 開陽、鷲ノ木より箱館入港。二十一発の祝砲。榎本・松平太郎ら五稜郭入り。
小野日記記述なし
|
| 12.15 | 二 | 石井略記 同二日福島を進撃す。海軍蟠龍艦我軍を援けんか為に福島の港二至り発砲す。敵是に気を奪はれ忽散乱す。
小野日記記述なし |
| 12.16 | 三 | 石井略記記述なし 小野日記同断 |
| 12.17 | 四 | 石井略記記述なし 小野日記同断 |
| 12.18 | 五 | 石井略記 同五日夜、勢揃ひ凱歌を作り、一時に松前城に迫る。此里数五里有と雖、途少も支へすして籠城す。直に攻む。
小野日記記述なし 函館100年 五日 土方隊は、松前城を攻略。藩主松前徳広はすでに館村(厚沢部町)の新城に逃れていた。 |
| 12.19 | 六 | 石井略記 同六日、三字の間にしてたちまち乗っ取る。城を捨て君臣共にアツサフ楯村の新城に及び江差の両口に落ちる。彼落ちるとき市中を放火す。半ば焼失といえども、たちまち鎮火して我が軍城中に入り大いに勝利の賀宴をなすと言う。
小野日記記述なし また直ちに尾撃し石崎の敵を破り江差に至り戦ふ。また回陽艦我が軍を助けんが為に来て放発す。敵たちまち蜘蛛の子を散らすが如く走る。 また我一軍一連隊三百人を率い松岡四郎次郎、二股の新道より進み稲倉石の関門に戦い敵嶮を守り拒戦すといえども、遂にこれを破り直ちに進んでアツサフ楯村の新城に迫る。これにおいて我が軍より松前公(松前徳広)へ使節(函館で降伏した松前藩士の桜井恕太郎)を遣る。 我が軍この地に来る状云々且つ、兄弟殺傷する益なし、元彼よりして我が軍を撃ち、やむを得ず遂にこの形至る。我が軍あえて戦いを好まざるなり。公向地に渡海せんと欲されば我が艦を以て速やかに送らしむなり。また共に恢復を計らんとの志あらば、共に援を乞うなりと言う。彼の重臣いう、衆議を尽くし速やかに答えん暫く戦を止めんを乞う。 然り我より言う、十二字まで答えなくんば手切りとなし速やかに兵を進め軍門において会せんと議して去る。然るに定約の節に至るといえども答えなし。故にまた進みて戦い新城を攻む、たちまち乗っ取り熊石に至る。これに於いて松前攻撃の軍と合兵す。此の時城主は関内宿より小舟に乗りし向地津軽領に渡ると言う。後に聞く、波荒く主船中にて死し、津軽薬王院に葬ると言う、実に可憐なり。松前の士、三百余人降伏す。各意を尋問しその意に任せ、或いは向地に送り或いは土地に残る有り。我扱う処議を以てす。後世恥じるなし。この戦に予出陣せず。故に詳らかに知らず。只報告を記す。ここに至る前一藩佐幕と王臣と論大いに沸騰し遂に佐幕論十余人を天誅す云う。蝦夷全島たちまち我が有となる。 これより先九日、我君公に及び唐津公、松山公鷲木より箱館に至り山口屋某本陣となしつ。 我ら新選組役を勤むる者に胴服赤フランネルを賜る。兵隊へは紫鵞絨(しがじゅう)のチョッキ賜る。これを以て一統寒気を凌ぐ。また榎本君より七飯村、我が戦功を称して士官に金五百疋、歩兵に三百疋を与ふ。また刀を以て敵を殺す者へは金千疋を与ふ。 かさねて、奥の仙領(奥州仙台領)石巻港より千代田艦、長崎艦、羽の庄内を援けんがため赴き、途にして暴風に逢い壮領(庄内藩)飛島に至る。長崎艦は遂に破す。実におしむべし。のち日数をへて千代田艦は全して函館に帰り来る。こに事件を告ぐる。よりてこれを助けんが為に弐番回天(秋田分捕り艦なり)を遣る。このとき谷口氏、荘内にある我が兵を迎えんが為、命によりて御直筆を奉りて共に発す。途に暴風に逢い走る能わずして翌日帰港す。 |
| 12.20 | 七 | 石井略記記述なし
小野日記 十一月七日 夕箱館病院人少にて、差支候間右へ移り候様申来候に付、翌八日朝出起箱館へ移り申候。病院懸りは相辞、外に何役なり相勤可申と申立候得共、松前は其以前手もなく落城、引続き、江刺も落去。敵は皆津軽地さし遁去りぬ。当分之處、戦争よりは病院大切にて、手負は勿論当病沢山に有之中には重き身分之者も有之。右進退をはしめ、烏合之大勢之病者取扱は、勿論医師ならず看病人勝手向未々に至迄、其外大細事悉皆取握一局之主宰に候間転じ難き旨に付、又々不得止任其意居申候。注:小野権之丞日記は、以下より明治二年二月二十三日までの間は維新纂輯四に輯録なし。 |
| 12.21 | 八 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 12.22 | 九 | 石井略記記述なし。六日の記述から これより先九日、我君公に及び唐津公、松山公鷲木より箱館に至り山口屋某本陣となしつ。
小野日記は纂録なし |
| 12.23 | 十 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし
函館100年
十日 松岡四郎次郎隊、館村の新城を攻略の為、五稜郭を発つ。(中山峠経由)
|
| 12.24 | 十一 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 12.25 | 十二 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 12.26 | 十三 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 12.27 | 十四 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし
函館100年
十四日 榎本、開陽で海上より松前・江差を巡視。
|
| 12.28 | 十五 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし
函館100年
十五日 館村新城陥落。 夕刻、開陽、暴風のため江差で座礁。
|
| 12.29 | 十六 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 12.30 | 十七 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 12.31 | 十八 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし
函館100年
十八日 開陽全員離船。
|
| 1.1 | 十九 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし
函館100年
十九日 夜、松前徳広青森へ。
|
| 1.2 | 二十 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.3 | 二十一 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.4 | 二十二 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし
函館100年
二十二日 熊石において松前藩士数百は降伏。これより前、乙部で土方・松岡は合流。 神速も江差で難破、数日後破船。
|
| 1.5 | 二十三 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.6 | 二十四 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.7 | 二十五 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.8 | 二十六 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.9 | 二十七 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.10 | 二十八 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.11 | 二十九 | 石井略記 同廿九日、我が隊松前に赴くべきの命有り。既発せんとす。然るにまた変じて止まるべきの命有り。
小野日記は纂録なし函館100年 二十九日 松前徳広青森で没。 |
| 1.12 | 三十 | 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1869年 | 明治元年十二月 小 | |
| 1.13 | 朔日 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし 注:以下 酒井孫八郎日記 墨文字表記 |
| 1.14 | 二 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 1.15 | 三 | 酒井日記 今晩出立之(手)筈決定。 某(それがし)並びに生駒傳之丞、林平右衛門の三人は横浜より海路箱館筋え。 五日立ちにて伊藤久輔・田辺國蔵・鈴木彌兵衞門右三人は陸路白川口より奥州筋え。 右の通り仰せ付けらる。 夜四半頃高橋脇より乗船、尾張藩小人目付高木六郎・精鋭隊銃卒渡部公次郎・貝沼儀兵衛三人つきそい同道。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.16 | 四 | 酒井日記記述なし 三日の記述から 翌四日明け六半頃横浜野毛町廣嶋屋え着す。四時過ぎ関門内え入り、平松屋寅吉案内にて米利堅九十三番ウエンリウトニ応接。夕刻引き取る。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.17 | 五 | 酒井日記記述なし 三日の記述から 五日、桑名や勘六方え罷り越し、野毛町三浦屋え引き移る。 石井略記 十二月五日、当隊は伝習士官と交代して函館を発し五稜郭へ赴く。屯所四ヶ所に入る。我二番屯所の取締を命ぜらる。毎日雪中を厭す(おしつぶす)仏式の練兵をなし大いに困す。榎本君より寒気を凌がんがために酒におよび鹿肉を度々与ふ。
小野日記は纂録なし
|
| 1.18 | 六 | 酒井日記記述なし 三日の記述から 六日、高木六郎、裁判所え罷り出で「出船免状」を受け取る。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.19 | 七 |
酒井日記 [横浜出港] 此の節、脱走兵箱館に割拠す故に、箱館え便船なし。 津軽青森えの便船英国蒸気船船名ソルタン、長さ三十五間程巾六間程三本柱。 右今日出帆の趣に付き、右え相頼み、一人につき二十五円充てで談判相整い候に付き、明五半頃野毛橋脇より押し送り船に乗り本船え乗り込む。英人・南京人等十人余・松前藩兵隊・津軽藩士家内引き移りども男女総計二百人余乗り込むなり。昼九時頃横浜出帆。波静かにして平穏なり。夜に入り風雨のため船の動揺甚だし。挙げ句船中の皆絶食に及ぶ。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.20 | 八 | 酒井日記 晴。風静(しずま)る。この日四方山を見ず。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.21 | 九 | 酒井日記 晴。今朝初めて奥州金華山を左方遙かに見る。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.22 | 十 | 酒井日記 暁雪来る。寒威殊に甚だし。昼過ぎよく晴れ箱館を右にして、左の内海(陸奥湾)に入る。内海に入りては箱館は全く後にあり。夕方七半時過ぎ奥州津軽青森港に着船。碇泊。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.23 | 十一 | 酒井日記 朝五半時過ぎ上陸。米町銭屋幸吉方に止宿。雪三尺程有り。市中皆軒下を通行す。家数三千程有りと云う。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.24 | 十二 | 酒井日記 夜雪。寒さ甚だしい。午後浜町会議所え傳之丞一同罷り出て、参謀太田黒亥和太え面談。薄暮どきに引き取る。 松前・箱館等全く脱兵の占有となり、彼らが押しよせて、清水谷侍従殿は黒石(青森県黒石市)に御在陣。当青森港に参謀肥後太田黒・長州山田市之丞が在陣。諸藩の官軍およそ二千人ほどが出張って来ているとのこと。この青森の地は、十月より降雪し、二月末まで続くという。今年は例年になく小雪ということだ。例年だと積雪は六尺あまりに及ぶと云うことだ。近在より日々馬にて米を市中にて売る。四斗俵およそ三百疋ぐらいである。魚は生の鱈・生鯡(にしん)・かな頭・まぐろ・帆立貝の類なり。酒は甚だ悪しく濁り甘みがあって重たい喉ごしだ。言語は甚だ聞きにくい。冬場は野菜無しといえども、塩あるいは漬け物にして貯蔵した蕗などを入れた汁を出す。生のものとさほど変わらない。男子の風俗は変わりなく、婦人は老いに至るまで、子供があっても眉を掏り落としたりはしない。青森港から弘前までの里程は十二里である。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.25 | 十三 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 |
| 1.26 | 十四 | 酒井日記 晴。夜雪。今朝箱館表え渡海の願付け添え、六郎を以て参謀え差しだし候ところ、 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.27 | 十五 | 酒井日記記述なし 十四日の記述から [箱館渡航許可出る] 翌十五日嘆願の通り御付け紙相済む。嘆願書委細は別帳参照。 石井略記 同十五日、土方君松前より箱館に帰来す。この日蝦夷平定するを祝し、弁天岬の砲台及び五稜郭、および軍艦、および各国艦、ことごとく祝砲百一発を放つ。実に愉快極まることなし。 小野日記は纂録なし |
| 1.28 | 十六 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 |
| 1.29 | 十七 | 酒井日記 [野辺地へ] 曇りのち雨。五半時生駒傳之丞同伴で出立。小いさな港で昼支度(ひるめし)。夜四時ころ野辺地え止宿。この駅家数五百軒程。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 1.30 | 十八 | 酒井日記 風雪甚だし。通行は遮断され滞留。寒威実に耐え難い。 石井略記 同十八日、魯国商艦を雇い再び庄内飛島へ遣わす。谷口氏もまた行く。荘の飛島に至り我兵を迎とするに庄内藩に逢兵隊の状を尋ねるに行方明らかならずと言う。遂に尋ぬる能わず。空布帰港す。実に残念なり。且つ彼の策も足しざる故なり。長崎艦に乗り組みたる神木隊は迎艦に乗し、七日を経て帰函す。長崎丸は破船すといえども乗り組みはことごとく無事にして上陸すといへり。
小野日記は纂録なし |
| 1.31 | 十九 | 酒井日記 同断(風雪甚だし。通行は遮断され滞留。) 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 2.1 | 二十 | 酒井日記 晴れ。風。五時ごろ出立。弁当持参。七時ころ横浜え止宿。里程四十八丁一里〆六里。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 2.2 | 二十一 | 酒井日記 晴れ。雲立ち。五時ごろ出立。七時過ぎ多那部(田名部=現むつ市)え。止宿。里程昨日に同じ。この宿家数およそ二百五十軒ほど。(後に戊辰戦争で賊軍とされた会津藩が領地没収の引き換えに斗南藩として再興が許された地) 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 2.3 | 二十二 | 酒井日記 晴れ。風。五時ころ出立。九時過ぎ津軽大畑え止宿。秋田藩と談判有り。 石井略記 同廿二日、五稜郭に於いて衆議を尽くし入札をもって役々を定む。その役に曰。
総裁 榎本鎌次郎 和泉守と改名
新選組長土方君、箱館取締に任ず。故に我が隊再び箱館に至り取締をなす。故に我が隊再び函館に至り取締をなす。町毎に屯所をもうけ夜巡邏を厳にす。副総裁 松平太郎 箱館奉行 永井玄蕃 陸軍奉行並 裁蕃為頭取、箱館市中取締兼 土方歳三 海軍奉行 新井筬之介 陸軍奉行 大鳥圭介 松前奉行 人見勝太郎 重任右の如し。余は未にことごとく記し、事今日月給を定、左の如し。
一 上等士官(指図役までを云う)金二両也
歩兵 金一両也一 中等士官(嚮導までを云う) 指図役下役 金一両三分也 嚮導 金一両二分也 一 下等兵士 一両一分也 予今日、嚮導役を転じて指図役下役となり市中取締命ぜらる。此の主なる役たるや、日々町局に出諸締向きを可り糺問に係す。常に在時は隊中の監察をなしまた外隊の応対を司り、会計の雑事に至るまでこの局に係ぜるはひとつも無し。 これより先、官軍函館にあるや太政官十三年限り金札幣を持ちいて来る、まさに通用せしめんとす。我が軍これを得るにあたりて通ぜずして捨て去る。我が軍これを奪う、その高五十万也。官軍この紙幣をつくり国中の通宝とする乎如是。紙幣を通宝と為し万民の困する事必然也。速やかに焼捨ん。直ちに市中へ布告して市民眼前、右五十万の紙幣を焼き払う。我が政府知に一分銀、二分金を製造す。その高二十五万乃至三十万に至る。これをして通宝とせしむる也。 我が軍この地を得るの後、諸事を寛大にし物を扱うに盃当を以てす、ゆえに蝦夷人大いに我に期せり。 今日外国艦将に託し朝廷へ嘆願す、その書曰 ・・・略
是に仏人「マルラン」来て我が隊に練兵を伝習せんと言う。故に毎朝六字より十字まで、弁天岬の砲台に於いて習う。雨天は本営に於いて技芸を習う也。小野日記は纂録なし |
| 2.4 | 二十三 | 酒井日記 晴れ。風。暮れ間際大間え着す。里程七里余。この辺は野生の馬が多い。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 2.5 | 二十四 | 酒井日記 [箱館沖ノ口着] 晴れ。東風。九半過ぎ乗船。夜四時過ぎ、箱館沖ノ口着。大町の大津屋(田中)庄右衛門方え止宿。海上七里。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 2.6 | 二十五 | 酒井日記 晴れ。今暁、脱兵側の沖ノ口懸吟味方小柴長之介・三浦省吾・書記方壱人罷り越し改め之有り。午後に成瀬・谷口等訪れ来る。 ○中将様(元桑名藩主松平定敬)当地神明社神職の家にますます御機嫌よく入られ候由。我が藩人およそ二十人ほどがお付きになり、それ以外の残りは庄内の方え引き離れ候とのことだ。 ○小柴長之介重ねて罷り越し、定法により、監視の番兵士官隊六人を配置し、両刀を相渡し候様申すので、それに従う。無用なトラブルを避け事を流暢に進ませるのが筋と考えたからである。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 2.7 | 二十六 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.8 | 二十七 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.9 | 二十八 | 酒井日記 今日禁固相弛み、中将様え拝謁の儀に付一封の嘆願書を榎本え差し出す。 石井略記 同廿八日、我君側の松岡孫三郎君、命によりて外国艦に乗し、潜に横浜に行き桑に至る。 小野日記は纂録なし |
| 2.10 | 二十九 | 酒井日記 折々雪。夜、新撰組隊長土方歳三来たり面談。 石井略記 同晦日、桑より酒井孫八郎、生駒伝之丞、君公の行方を尋ねんがため、官軍に乞うて奥の青森港より函館に渡海す。彼れ桑城の衆議を述べて曰、 桑家滅亡、君の一身に関係す。ゆえに桑行き謝罪せらるべしと言う。 君公曰、我が為に多くの家臣塗炭の苦しみをなすに至っては実に忍びん、しからば謝罪せん。 随従の士曰、今君桑行き謝罪すれば幽閉せらる、必然也いかがぞ。君をして敵に出す、臣として忍ばざる也。元は徳川ありて桑家あるなり。今は徳川氏かくそしりを請くれば、臣死の義ならん乎。たとえ桑家滅亡すといえども、義をもってすれば天下に愧ずべからざるなり。
酒井氏皆勇気満々たるを見て敢えて論ぜず。君衆議の宣布に託す、議遂には決せず。 [酒井日記ではこの日はまだ面会できていない。]三公居所を分けて我公、神明神主沢辺一馬宅に遷らるなり。 小野日記は纂録なし |
| 1869年 | 明治二年一月 大 | |
| 2.11 | 元日 | 酒井日記 晴れまた雲立つ。大町大津屋方に止宿。朝、屠蘇雑煮など差し出さる。夜には土方歳三・小柴長之助罷り越し面談。この日両刀受取、即夜に士官隊五人の付添のもと、山の上の神明社神職之宅え護送せらる。君上の御座所也。引き渡しあい成り直ぐさま御目見え仰せつけられ御前に出る。夜半大津屋え引取る。むろん生駒傳之丞も同様である。この日より日々御座所え伺う。 石井略記 明ければ正月一日、予公に拝し年賀す。公より祝杯を賜ふて愉快をなす。
小野日記は纂録なし |
| 2.12 | 二 | 酒井日記 大町の松尾屋八郎方移転寓居。御座所に於いて、追々小笠原侯(元老中格小笠原長行)・板倉公(元老中板倉勝静)え御目見え。 石井略記 同二日、我隊市中大巡邏をなす。
小野日記は纂録なし |
| 2.13 | 三 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.14 | 四 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.15 | 五 | 酒井日記 元会津屋敷下長屋に寓居。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 2.16 | 六 | 酒井日記 本陣え罷り越し、榎本泉州え面謁。又候(またぞろ)大町の丁サ印(場所請負人佐野専左衛門の萬屋の店章)の店に寓居する土方歳三を相訪ね面談・・夜引き取る。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 2.17 | 七 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.18 | 八 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.19 | 九 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.20 | 十 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.21 | 十一 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.22 | 十二 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.23 | 十三 | 酒井日記 御決定の儀之有り。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 2.24 | 十四 | 酒井日記 土方・榎本え罷り越し面談。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 2.25 | 十五 | 酒井日記記述なし 石井略記 同十五日、陸軍隊故ありて青山次郎を長となし兵士二十人、歩四人を率いて新選組に加入す。また彰義隊より兵士八人加入す。
小野日記は纂録なし |
| 2.26 | 十六 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.27 | 十七 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 2.28 | 十八 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.1 | 十九 | 酒井日記 土方え罷り越し面談。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.2 | 二十 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.3 | 二十一 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.4 | 二十二 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.5 | 二十三 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.6 | 二十四 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.7 | 二十五 | 酒井日記 同断(土方え罷り越し面談。) 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.8 | 二十六 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.9 | 二十七 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.10 | 二十八 | 酒井日記 同断(土方え罷り越し面談。) 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.11 | 二十九 | 酒井日記 榎本え罷り越し面談。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.12 | 三十 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 1869年 | 明治二年二月 大 | |
| 3.13 | 朔日 | 酒井日記 榎本え罷り越し面談。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.14 | 二 | 酒井日記 榎本え罷り越し面談。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.15 | 三 | 酒井日記 同氏(榎本)え御直書被遣。 [松平定敬、榎本へ直書を送る] 土方え罷り越し面談。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.16 | 四 | 酒井日記 土方え罷り越し面談。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.17 | 五 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.18 | 六 | 酒井日記 榎本、御座所え来たり便船の談あり。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.19 | 七 | 酒井日記 生駒同道で本陣え罷り越し、榎本と面談。仏人ウエウユに応接す。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.20 | 八 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.21 | 九 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.22 | 十 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.23 | 十一 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.24 | 十二 | 酒井日記 松平定敬様が英学御修業のため池田溌三郎方え入塾なさられ候に付き、某(それがし)また供奉しつつ修業を始める。これより日々罷り越す。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.25 | 十三 | 酒井日記記述なし 石井略記 二月十三日、加州の帆船に乗じ事有りて潜に桑行す。
小野日記は纂録なし |
| 3.26 | 十四 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.27 | 十五 | 酒井日記 生駒傳之丞が御内用で出府命じられた為、仏人ウエウエが引き受けてくれて今日乗り込み出帆した。 石井略記記述なし 小野日記は纂録なし |
| 3.28 | 十六 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.29 | 十七 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.30 | 十八 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 3.31 | 十九 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 4.1 | 二十 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 4.2 | 二十一 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 4.3 | 二十二 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記は纂録なし |
| 4.4 | 二十三 | 酒井日記記述なし 石井略記 同二十三日、君公、予輩皆率いて蒼海楼に登り(海岸の料店にして絶景)各自盃を賜り或は舞い、或は踊り、或は詩を吟じまた歌うあって、おのおの得るところの技を出して大いに愉快を極わむ。 小野日記 注:以下 会津藩士 小野権之丞日記(明治二己巳年日記) 小豆色文字表記 二月廿三日 高龍寺引き払い病院へ移る。天気好。竹中殿被参。夜に入り三浦来る。 |
| 4.5 | 二十四 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同廿四日 朝の内少々ずつ両三度雨降り後天気。 ○朝竹中殿高龍寺へ参る。 ○高龍寺礼に来る。 |
| 4.6 | 二十五 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同廿五日 終日雨。昼前本陣へ出る。川村、高橋に金米普請の儀申談。従夫(それより)、運上所に行く。午帰る。 ○昨夜五ッごろ仏の交代船入港す。昼後兼約にて高龍寺へ行く。渋谷侯はじめ御参会。御帰りがけ一色侯へ御出につき参る。 |
| 4.7 | 二十六 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同廿六日 天気。仏船交代御多忙のところ俄に今夕に相なる。夕、井上、石田参る。 ○昨日佐久悌、並河来る。 |
| 4.8 | 二十七 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同廿七日 晴れ。諏訪より手紙田村持参。夕、高松氏下宿移りの事。 |
| 4.9 | 二十八 | 酒井日記記述なし 石井略記 同廿八日、予市中取締行きとどきを称して、土方君より金千疋を与う。 小野日記 同廿八日 晴れ。昼後、本陣へ出る。佐久悌へ病者の儀申談。 |
| 4.10 | 二十九 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同廿九日 晴れ。風にて寒し。昼後、本陣へ出る。台所普請の入札開く。福嶋へ返事二度分差し出す。暮れ以前またまた本陣へ。出金三両受け取る。普請仕様帳絵図下る。 |
| 4.11 | 晦日 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同晦日 晴れ。夕、高龍寺へ参る。右寺病院是まで通り心得呉候様之儀談す。夜、正廣_見。 |
| 1869年 | 明治二年三月 大 | |
| 4.12 | 朔日 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同朔日 雪。風寒し。一昨日英商船入港之由。大坂船先日より二艘入る。 |
| 4.13 | 二 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同二日 昨夜より積雪二寸ほど。終日認物。 |
| 4.14 | 三 | 酒井日記記述なし 石井略記 三月三日、君公少々御不例にして大いに心痛す。公もとより騎することを好みたまう故に、予、鹿毛六才なる駒を献す。公おおいに悦したまい快せられて、後、これに乗じて市中遊歩せらる。
小野日記 同三日 晴れ。四ッころより井深。従夫、会計へ出る。岡崎へ参り帰りがけ焼け跡辺より雪にあう。夕にまたまた晴れ。佐久間来る。三宅、岡崎来る。佐久間一同土方へ。同人より手紙越候儀につき罷る越し候ところ最早出起につき佐久間方へ罷り越す。暮れて帰る。 |
| 4.15 | 四 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同四日 晴れ。四ッころ、青柳へ。福嶋行きの儀につき参る。帰り候ところ土方より手紙来候につき即刻罷り越しそうらえば、留守なり。よって佐久間へ罷り越し帰りにまたまた土方旅館へ立ち寄る。それより称名寺へ尋ねられにも不居候につき帰る。夜中同人への手紙認める。昼前、岡崎、井深来る。正廣刀。 |
| 4.16 | 五 | 同五日 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 陰晴れ不定。小雨来ることあり。早天(あけがた)佐久間悌二へ出、土方への手紙相頼む。夕、三宅、三浦、朝倉、田嶋ら来る。岡崎も。 |
| 4.17 | 六 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同六日 雨。夕晴れ。朝、英船入港。一昨日ころ市中片付け始まり、今日方頻りなり。岡崎、永井殿子松本来る。 |
| 4.18 | 七 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同七日 朝晴れ、夕曇。柏崎より高松氏へ手紙来る。福嶋行医者の儀なり。夜中右返事認め添え書きも認む。朝、東條来り存意咄す。能州船入港候由。夕、英の帆前船入港。 |
| 4.19 | 八 | 酒井日記 朝五ッごろ御座所え伺う。松岡孫三郎・後藤多蔵・金子屋寅吉、微行(おしのび)で昨夜着き面談。(明治元年十二月二十八日 定敬同行の松岡孫三郎は定敬の命により外国船に乗って密かに横浜へわたり更に桑名へと向かっていた。) 石井略記記述なし 小野日記 同八日 雨、昼後よりおいおい天気。昼後、竹中殿より手紙来る。湯治行の由につき即刻参る。桑藩人着候につき、直ちに罷り越し候ところ、松岡孫右衛門、後藤_両人なり。様子承り七ッころ帰る。青柳福嶋行に話定む。本陣より手前出す。朝、柏崎へ手紙出す。 |
| 4.20 | 九 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同九日 天気。昼前会計へ出金催促す。青柳噂の儀も申す。柏崎より返事達す。竹中殿今朝出起。 |
| 4.21 | 十 | 酒井日記記述なし 石井略記 同十日、松岡孫三郎、桑より金を携えて帰函す。後藤多蔵、金子屋寅吉共に来る。後藤氏・・・ (以下略)
小野日記 同十日 晴れ。青柳出起に付き昨日認。諏訪訪へ書状さし出す。晴れに付き、昼後より山へ登り四方眺望を志し出起連を尋ね候ところ幸いに山本に逢い案内いたし呉一樽を携え呉一番観音のところにて開く。俄に東風起こり寒につき山下へ下り開莚中、桑藩人ならしき者両人来。帰りに竹芝に寄り山本に報礼す。其の中雨に成り同所より傘借り七ッ半前帰る。 |
| 4.22 | 十一 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同十一日 追々天気。昼食後本陣会計へ出金百五十両受取帰りに道具屋へ寄り品々一見。七ッ前頃帰る。帯直し頼む。 |
| 4.23 | 十二 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同十二日 快晴。高橋辰次郎湯治に出起につき柏崎へ手紙差し出す。 ○庄内より加藤章太郎帰り候。人尋ね来る。両人■。 |
| 4.24 | 十三 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同十三日 晴れ。異人ども都合四人来る。夕、英蒸気船入港。 |
| 4.25 | 十四 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同十四日 雨。夕より晴れ。伊庭八郎来る。夕、榎本被参談判有り。 |
| 4.26 | 十五 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同十五日 暁雨。朝より晴れ。夕七鼓ころより三宅参り呉候様申すにつき参り候ところ養子いたし候につき神酒相備え候由なり。 ○昨日の咄に付き病者ども帰し、しかるべく心付け高松氏に様子承る。 |
| 4.27 | 十六 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同十六日 晴れ。風。朝、井深方ヘ参り帰りの儀申談。岡崎、坂井来る。酒差し出す。昼後、三宅に被誘またまた一供にいたし七面社より十■(Thomas Blakiston)之庭一見。同所にて一飄開し。一昨夜榎本総裁の認めと相なり候書き一覧。従夫、谷地頭へ参り帰りに井上方へ立ち寄帰りの儀申談一同へも同人より可申談呉旨共々及談判またまた可立寄勘定いたし七ッ半ころ帰る。 |
| 4.28 | 十七 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同十七日 晴れ。暖。和風。暁三帆の小船入港。長鯨出帆。三宅より手紙遣候につき一郎罷り越し、金子三十両借り受け。昼食致し帰り直ちに本陣へ出る。従夫、間澗口へ参り正廣刀求。帰りがけまたまた可参り七ッ時過ぎころ帰る。 |
| 4.29 | 十八 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同十八日 山瀬風雨夕荒れ模様。刀またまた一口遣す。フリウネ来る。 |
| 4.30 | 十九 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同十九日 晴れ。風。本陣荒井郁之助より先生へ手紙遣わし候につき被出候ところ、宮古に掛かり居る惣鉄船襲打乗っ取りの策に候ところ、蟠龍丸医遠山春平儀不快にて罷り越し兼ね候間、病院より何と歟繰合を以、壱人医師遣し呉候様との談事に付、右の段内談有之候故、赤城に及び内談候處罷り越候儀承知に付彌取極に相成。初夜に乗船につき蟠龍まで蓮沼一同送り参り、船将松岡に逢引渡帰る。松本来る。戻り候得は無程帰る。船今夜出帆の筈に候ところ如何に候哉延びる。 ○明朝出起の由にて田村来る。 |
| 5.1 | 二十 | 酒井日記記述なし
石井略記同断
小野日記 同廿日 晴れ。風あり。回天、蟠龍丸、アシュロットの三艘昨夜出帆無之。六日英船より応接済之由にて右船八ッ時出帆なり。右出帆に相成候に付き今夜三艘出帆の由。田村来る。金をねだる。壱両用立て遣わす。諏訪への手紙認める。 |
| 5.2 | 二十一 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 [写真] 同廿一日 快晴。三艘の船今暁出帆の由。昨日認め候書状ちょっと書き添え同時来を待ち候ところ、来候らわずにつき、午前、町会所え差し出す。昼午、歩行に出る。三宅を誘い候ところ留守につき、芝の前を通行の砌(みぎり)尋ね候らえば、居合わし候につき、立ち寄り候ところ、写真いたし候につき、見物に参り候ところ、写真可遣(遣=送る、遺=残す・贈る)旨立而(たって)申すにつき、相頼む。従夫(それより)、井上、石田、一同で岡崎へ尋ね参る。留守なり。帰りがけ武蔵野へ立ち寄り柏崎を尋ね候ところ居らず候。別れ候。しこうして、山瀬泊まり方まで遊歩。七ッ半前頃帰る。諏訪より書状相達し居る。総督えの返書も一同来候につき添え書きのうえ差しだし候事。 |
| 5.3 | 二十二 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同廿二日 極快晴。風無く別而静也。暮れ方より変わり模様になる。 |
| 5.4 | 二十三 | 酒井日記記述なし 石井略記 同廿三日、少く激する事件あり。夜、我が回天、蟠龍、二番回天(高雄)右三艦をもって、奥の桑ヶ﨑(南部領なり)に碇泊するところの官の鋼鉄艦を奪わんと欲し、陸軍奉行並土方君、および添役相馬氏、外三輩に、兵隊は神木隊、彰義隊、遊撃隊の三隊数百人、仏人「ニコール」「コルラッシュ」これに乗じて発す。ああ不幸なるかな、途にして暴風にあい艦まさに覆らんとす。故に二艦は後れ独、回天のみ。
小野日記 同廿三日 昨夜中より雨。 |
| 5.5 | 二十四 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同廿四日 雨。午より晴れ。 |
| 5.6 | 二十五 | 酒井日記記述なし 二十六日の記録から 回天丸、南部桑ヶ﨑港にて官軍の軍艦八艘と戦闘。 石井略記記述なし 廿三日の記録から 廿五日、桑ヶ崎に至。暁天敵の八艦の中へ疾駆し直に甲鉄艦を衝く、其勢ひ恰も雷電の激するか如し。甲鉄艦将に覆らんとす。我回天の巨砲五十六斤を以て鉄艦中へ二発を放ち、是の機に乗して数人提刀躍り入り烈戦、殆奪んとすと雖、鉄艦も亦録して其備あり、且他艦より頻に発砲す。遂に奪ふ能すして回天一艦を以て八艦中縦横に西奔東進し、遂に退けり。
小野日記 同廿五日 朝薄曇り。夕晴れ。本陣へ出候ところ金子明日まで延べ呉れ候様との事也。帰り懸す丸之辺梅花一見す。 |
| 5.7 | 二十六 | 酒井日記回天丸帰帆。昨二十五日朝、南部桑ヶ﨑港にて官軍の軍艦八艘滞泊の中え乗り込み二時間ほど苦戦のうえ引き上げ帰帆した。蟠龍丸・二番回天丸共三艦相向かい候ところ風雨に出会い、回天のみ早く到着し交戦。他の二艘は間に合わず、蟠龍丸は途中より引き戻り今夕帰帆した。回天丸船将甲賀源吾を始め副将並びに乗り込みし者じつに十八人討ち死。内二人は官軍艦船へ乗り込み討ち死、壱人は洋中に堕ちる。負傷は三十二人有ったという。二番回天丸の様子は相聞かず。官軍死傷も少なくはない様子と相聞く。 石井略記記述なし 廿三日の記録から 廿六日に至り帰港す。蟠龍、後れて至ると雖、回天の退くに当て共に退き帰港す。二番回天は此状を知らすして行く。然るに敵の数艦進み来り力戦すと雖、力尽き已を得す艦自焼して神木隊、仏人「コルラッシ」共に上陸す。蓋し官軍の為斬獲せられん未だ其処する所を知らす。此時回天の威名敵中に轟き艦将甲賀源吾、檣(しょう)上に在て指揮す。彼れの弾丸腕と股とを貫く。尚令を止ます弾又胸を徹し死す。副将矢作沖丸も共に働き死す。相馬氏鉄艦に入り傷く。故に新選組野村氏、直に是を我艦に抛(な)げ上げ自ら数人を斬り、将に退かんとするや敵其背を衝く。水中に没す惜む可し。仏人「ニコール」傷く。死傷数十人。彼れの一艦大に破壊し東京に赴き終すと言。我回天、三発を貫と雖、運転するにさはりなし。此時、英の軍艦是の港に碇泊在り、共に回天に砲発する。回天大に怒り直に進て三発を故ち、彼艦を貫くと言。悪む(にくむ)可きの甚敷者(はなはだしきもの)也。
小野日記 同廿六日 晴。四ッ半前金子為受取本陣へ出、帰りに高松氏見舞、午過る頃帰る。一時頃、回天戻り入及一覧居候内、赤城帰り来り。手負に十人余入院之儀申す。同人一同高松氏へ參り申談。当病軽き分二十七八人出院之上設いたし追々入院扨。昨暁より回天にて岬へ進み、明け候得は惣鉄船へ無二無三にアメリカ之印を揚げ候。而乗付、偖(さて)船より伺見る内に、印を変し打懸る。右船え五人程切入五十ポンド二発打込、一発はかまを目がけ打込候處烟出し曲り、一発も能きき候と見六七人被打揚候由。賊船飛龍丸、武蔵丸、薩之春日丸、土之ゴンホ、肥前の鐵船、芸のしん天丸外に鉄船一艘とくわ之湊に掛り居。右船々より如雨霰大砲小銃打懸、船も所々に当り候へ共、要所には不当候由。之よし鐵船にふれ候處少し損候由。討死十八人、手負三十に人にて頗る烈戦一時間程之由。アシュロット、蟠龍は、しけ(時化)に逢い候節、互に相失し、戦終り引取之節、湊口にて行逢合図にて為引戻。蟠龍も又少々手前にて逢候由。二艘共事に不逢を残念かり、二艘にて打懸之策も有之候得共、強而(しいて)差留候由也。夕刻蟠龍も戻り来る。○諏訪より書状昼少前達す。大鳥、井上、並川等へ之書状共相届け候。 ○病人共出院大勢取計手負病人共入院。 ○夜中諏訪へ之返事認。 同廿六日 晴。諏訪へ之返事、町会所へ差出早朝也。松平太郎殿フリネ来る。 ○昨日より高松先生不快也。 |
| 5.8 | 二十七 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同廿七日 晴。病人へ見舞大勢来る。榎馬、荒井郁之助等も来。夕、瀧川等来。失敗之挙動有之候に付不為通差戻候事。 |
| 5.9 | 二十八 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同廿八日 晴。永井玄蕃頭、大鳥圭助入来。諏訪より廿六日出書状相達す。金子返る所々え之書状相届候。 |
| 5.10 | 二十九 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同廿九日 晴。榎本總督被參候。蟠龍水夫始死人有之。 |
| 5.11 | 晦日 | 酒井日記記述なし 二十六日の記述から 三十日より御座所え止宿。 石井略記記述なし 小野日記 同晦日 曇。曾計へ出。去月中迄之帳面持參致す。並河来。明日起之由也。 |
| 1869年 | 明治二年四月 小 | |
| 5.12 | 朔日 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 四月朔日 朝晴。総督被參病者へ金子賦りに相成。昼後八ッ半頃より並河へ可參高龍寺立寄酒に預る。従夫、途中にて逢。諏訪へ之書状相頼。柏崎武州楼に居候由に付、相尋候處帰りに相成候さ而加藤に逢。帰り懸け兼与へ立寄並河に逢。 |
| 5.13 | 二 | 酒井日記記述なし 石井略記 四月二日、追々切迫に及、又君公、進退の儀に付再ひ論起る。或は公の進退嘗て榎本氏に託す。今私に進退を定む可さる也、と言あり。或此地に止まられ、臣と共に尽力せらる可しと言あり。或は潜に桑行の議あり。予答日、今函館の我軍、海軍は已に敗れ陸軍は限り有るの兵を以、限り無きの兵に敵す。一勝有と雖遂に敗せん事必せり。爰に(ここに)於て考るに桑行函囚と成るも忍す。又爰に死を潔するに非す。故予思は、一度外国に潜居し時を得は、春、龍天に登の会も有可き也と。遂に衆議洋行に決す。是を「メリケン」公使に談す。彼れ日、君公は我に託よ厚意言々、然に今航するの艦無し。不日に来るの約有り。是に尽力すと言。此議榎本氏に談す。彼の論も云々有と雖遂に洋行然る可しと決す。
小野日記 同二日 可也之天気。会計より薬品共遣す。八ッ半頃諏訪より之手紙。並河へも遣候に付、早速相送り候處、四ッ時頃出起之由にて返す。高龍寺より竹中殿へ之手紙遣候に付町会所へ手紙添差出す。 |
| 5.14 | 三 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同三日 曇。昼以前より雨雷鳴。諏訪へ手紙。並河書状返す。川村録来る。 |
| 5.15 | 四 | 酒井日記記述なし 石井略記同断 小野日記 同四日 朝曇。五ッ半過頃より晴。昼食後、小黒、佐野一同一瓢にて山へ登り。観音之處にて一望。従夫、頂きえ登り四方眺望殊に好同所にて開き。従夫、山傅にしりさわへ下り、鮮魚求候處不猟にて無之に付、谷地頭へ廻り、右茶屋相尋候處いずれも休み居り、埓明き不申候に付、梅花李花を折、右道々、休み茶屋之椽をかり酒相用い、暮に帰る。 |
| 5.16 | 五 | 酒井日記 山の上十升(Thomas Blakiston)の花園見物に罷り越す。草木いろいろ有り。梅花盛り、桜は微かに開く。 石井略記記述なし 小野日記 同五日 雨。八ッ半頃より少々直り暮以前上る。柏崎より手紙遣し。六字頃より武州楼へ參呉可申旨に付、夜食後參る。出懸、岡崎氏え立寄候處、朔日より留守也。加藤章太郎一同酒給へ。夜半過帰る。 |
| 5.17 | 六 | 酒井日記 榎本え罷り越し面談。官軍より期日指定無しで進撃の布告之有り。市中動揺不大方。 石井略記 同六日、英国の商艦(アラビヲン船の名なり)奥の青森より官軍に意を受来り曰、
小野日記 同六日 晴。八ッ時頃俄に風起り暫時雨。六ッ半頃、英之赤船入港。右船へ木村来り候由に付、赤城承りに出る。触有而町中不一と方騒也。暮合より木村尋ねに出る。結城繁樹、松前より来候趣に付尋来候に付、鹿酒(粗末な酒)差出一同に出る。柴を尋候處不居。蛇足に居る歟不知候に付、同人一同にて罷越候處、三宅、三輪居る。津田主計も来り、同店にて酒差出。一同帰る四ッ時頃也。曾て布告せし如く、追討の為に官軍此地に来る近きにあり。各国在函の者は今より西洋廿四時の間に家具を尽く青森に運遷し、各其艦に乗し函館を発し出つ可し と言。総裁より我軍戒を厳にし、且市中に示し立退き場を設て遁去せしむ。
|
| 5.18 | 七 | 酒井日記 [松平定敬蝦夷脱出行] 晴れ。六半時ころ定敬様お発ち。それがし・成瀬・松岡供奉す。後藤・金子はお見送りの為の随従。七飯村にて昼支度。七ッ過ぎ峠下大畑屋に止宿。 石井略記 同七日、十二字(時)、各国悉く函港を発す。市中も担を負ひ臥牛山の服々に去り、一時大に雑騰、忽ち寂寥たり。我病院市中にあり。「アメリカ」人「ライス」是を預り国旗を掲て番兵を付く。仮令(たとえ)敵地と雖奪能す。爰に新選組弁天岬の砲台に入守る。
小野日記 同七日 天気。市中大に騒々しく取片付頻り也。四ッ頃より木村尋に柴へ立寄候得ば、柴居り面会。木村来。意大抵相分る。従夫、本陣へ出、病院不移一條及挨拶。序に金之及談事候處、夕刻可出旨也。昼頃帰る。結城今朝出起之筈也。八ッ頃より七面社辺より崖高く登り、市中一望之積にて出懸け候處へ、三宅、三輪来る。立戻り候處、明日松前之方へ出起に付暇乞也。両人帰り後、七面社へ登り候得ば、瀧川、宮内等婦人数人召連、見苦体に付不立寄。同所橡にて遠望。山瀬泊之方より高龍寺脇へ廻り、市中之様子一見。七ッ過頃帰る。食事後午後早速異船共不残出帆。此砲台は曾て魯国人の縄墨を以巨石を積み之を築く。高さ九間、周囲五丁、其形恰も削か如嶮也。鼠能梁を健にして走ると雖、仰て登るあたはず。堤上に巨砲八十斤、及に十四斤を備、且堅にして鉄艦の三百斤と雖破砕するを得す。塁下湘々(びょびょう)たる蒼海白波岸を打つ。臨者皆戦慄す。 予、差図役下役を転し本官と成る。兵士拾二人を与ふ。我軍曾て守る処の寒川(西の背面の海岸要地なり)、十番ノ観世音(臥牛山の上にあり、函館の左右を眼下に見下し入津を見張り肝要の地なり)、東風泊を守る。又一分隊十番を守る、又一分隊沖ノ口を守る、一伍其他は砲を守る。夜中役々、番兵所市中巡邏厳にす。 ○下陣金為受取出候處、榎本泉州も參り被居。従夫、三宅へ為暇乞出る。四ッ頃帰る。ユコル留主中に■宅へ引移りし由也。 |
| 5.19 | 八 | 酒井日記 曇り。五過ぎ出立。伊賀伊川にて昼支度。七時過ぎ森村にて止宿。 石井略記記述なし 小野日記 同八日 曇。山瀬風。賊不来。 |
| 5.20 | 九 | 酒井日記 風。滞留。(官軍江刺に上陸) 石井略記記述なし 小野日記 同九日 曇り。小雨折々降。夕、心祝い致す。賊六艘松前へ廻り候由注進有之趣也。 |
| 5.21 | 十 | 酒井日記 同断(風。滞留。) 官軍八艘昨朝江刺え押し寄せ容易に上陸、(脱軍の防御施設を)乗っ取りに相成り候とのこと。 石井略記記述なし 小野日記 同十日 曇。八ッ半頃より蓮沼、田中、佐野一同一瓶為持十升(Thomas Blakistonの植物園)桜花見に出る。大山上にて開瓢。諸人来。従夫、七面へ上り、同所茶屋にて一同酒給へ折節夕陽晴東北山に映し眺望殊に宜し。川村来候に付、金子之儀申談。蓮沼はニコル之處へ參候に付、田中一連には分れ、佐野一同所々遊歩。暮に帰る。 |
| 5.22 | 十一 | 酒井日記 晴れ。五過ぎ乗船出帆。夕刻モロラン(室蘭)港口まで罷り越し候ところ、仔細之有りて直ちに帰帆。夜船中にあり。 石井略記 同十一日、官軍八艦を以て江差(松前より蝦夷地の方へ寄所也)方面に進来す。我軍少兵を以て防戦す。尤勉と雖遂に乙部邑(江刺より蝦夷の方による)守兵無きを知り是より二千余人上陸す。直に海陸軍を以て江差を差て襲来す。我軍彰義隊大に奮烈戦すと雖、兵僅しして防き難く遂に敗して江差も敵の有と成る。
小野日記 同十一日 快晴。朝、木村来る。昼食まで談話。○君上御機嫌伺始品々承る。 |
| 5.23 | 十二 | 酒井日記 今暁、砂原村え着船。直ちに出立。峠下にて昼支度。夕刻亀田え着。民家に宿。 石井略記記述なし 二日の記述から 后十二日、艦を得、酒井氏、松岡氏、寅吉随従して函港を発せらる。皆港に公を送る。爰(ここ)に於て別杯を賜ひ皆言上して曰、
小野日記 同十二日 晴。四ッ頃より柴方へ參り、昨日之儀品々申談す。岡崎氏、山田来。酒給。正午帰る。蒸気異船有川方に当り滞舶す。生前の離別是を限りと為。後必潔戦死を以厚恩に報せん。 遂に流涙離別と為る。後、艦、横浜に至り艦を替て已に発せんと、然るに桑より爰に来る者あり。君を止て遂に謝罪と成る、実に切歯すと雖、隔地止む能す。実に遺憾極無き也。石井略記 廿一日の記述から 是よリ先十二日、彼れ江刺よリ新道を進てニ股村に迫る(函館へ出る間道也)。是を守る我軍、伝習士官一小隊、歩兵一小隊、衝鋒隊三小隊、合僅二百余人也。敵は薩、長州、津軽、備ノ福山、松前、備前、合ては六藩、人員五百余と言。爰を以て屡攻む。我軍嶮地に胸壁を築て泰然として守る、又五稜郭より一小隊を以是を援く。軍気益振ふ。敵屡攻むると雖、我軍地理を得る、且土方君将たれは能機に応し勉強して防く。彼れ只死傷するのみ。 |
| 5.24 | 十三 | 酒井日記 [松平定敬箱館脱出] 晴れ。未明箱館港より米利堅帆船前船乗り込み直ちに出帆。 石井略記記述なし 小野日記 同十三日 小晴。額兵隊三人キコナイ之戦に手負候由にて来。戦は末だ全く勝利迄に不至内出起候得共、多分勝利に可有之趣也。八ッ半頃より七面社、愛岩山遊歩。八幡社迄參り大町へ出。七ッ半頃帰る。無程、俄に曇り雨。夜中西風に変じ、風甚敷雨。 |
| 5.25 | 十四 | 酒井日記記述なし 石井略記 同十四日、仙藩二ノ関源二、見国隊四百余人を率ひ英国商艦(エーレンバック)に乗し、蝦夷地佐原港(函館をへる七里余也)脱し来る。我軍大に力を得る。然るに我藩人共に来ると告る者あり。皆大に悦。
小野日記 同十四日 晴。三宅、三輪松前より手負引連れ船にて着之由。五ッ時過頃来る。仍而多勢にて六拾人余之由に付、高龍寺仮病院之談事にいたし、早速、夫々取計を付け、高龍寺へ談事に罷出る。皆着之上には病院へ入込候儀相叶ッ候付断返し。松前表も勝利キコナイも彌勝利之由也。鈴木元三郎来候に付、引揚之儀及議論候處少し譯有る義也。夕に至り二岐之方も亦勝利之由手紙にて申来但出張之添役より也。石井略記 廿一日の記述から 然るに十四日、敵大軍を以て奮戦す。我兵殆と敗せんとするを以て大に奮発接戦す。此役二日三夜の大戦遂に敵軍を破りつ。 |
| 5.26 | 十五 | 酒井日記 晴れ。南風。夜、無風。月明かり也。ようやく南部宮古の沖に至るが船は動かず。 石井略記記述なし 十四日の記述から 翌十五日暁天、予森駅(函館へる事八里ほど)迄是(十四日参照)を迎んが為馬を馳行、十二字に達す。然に木村忠次郎、山脇隼太郎、高木剛次郎、土田外真記、長瀬清蔵、右五士来り面会す。
小野日記 同十五日 晴。岡崎来。松平太郎殿為見舞被参。土田氏は始会也。山脇氏、高木氏、木村氏は朋友也。会城の敗にあたりて別れ今日に至る迄安否を知す。然るに互に命を全して爰に会す。実に悦喜に堪さる也。共祝杯を傾け其故を尋るに、山脇、高木両氏は荘内屯の我兵隊より内意を請て来る。通路難きを以て僧と為て来る。木村氏、長瀬氏は予輩仙に在る時、山形城下より隊命に依て君を尋奉らん為に来り。吾等会て又帰る。然に途官軍のさゝヘる処と為り通路無きを以て止を得す、遂に仙に潜伏して時を待つ。然るに高木、山脇仙に来、途にして風と会し共渡海すと言。土田氏は桑を脱し仙に来り。是又天幸にして諸士に会し共来ると言。爰に於て予諸方の状実を詳に知り直に皆同道して函館称名寺、我隊の本営に遇する也。 ○七面社。 |
| 5.27 | 十六 | 酒井日記 晴れ。南風。夕刻、桑ヶ﨑港え入いり碇泊。 石井略記記述なし 小野日記 同十六日 晴。回天丸始出帆に付、夜食後高松氏へ同見物に出、帰りに右下宿へ寄る。 |
| 5.28 | 十七 | 酒井日記 晴れ。暖気なり。今日も滞船。 石井略記 同十七日、江差の我軍、奮激数々戦ひ少利有て夫ふ処の地を得ると雖、敵海陸軍より頻に進来。遂に松前城に龍り防戦すと雖、少兵を以海陸に敵し遂に力尽き此城敵の有と成り残念なりと雖退て尻内峠を守る。此時我軍死傷多し。敵は勢ひに乗して進み、峠にて防戦す。又利あらすして二里を退き木古内を守る。我軍戦毎に不利にして、且一軍は福島に有て敵中に孤立し出る不能。故に木古内村の我軍、大に激励して尻内、木古内の両道より夜襲し奮戦、大に敵軍を破り孤立する処の一軍を救ひ、又失う所の地を得る。木古内邑はニ里余進て大嶮の峠を守る。然るに尻内村は地に嶮無く守る能さるを量り退て当別村を守る。是陸軍奉行大鳥主介氏の量る処也。後復、戦不利にして退き茂辺治村を守る。
小野日記 同十七日 晴。十升(Thomas Blakistonの植物園)參り。従夫、井深居宅相尋、山本參り帰りに、三宅旅宿相尋暮以前帰る。 |
| 5.29 | 十八 | 酒井日記 晴れ。北風。未明五時ころ出帆。 石井略記記述なし 小野日記 同十八日 晴。早朝木村来。越国廻り船乗船之心得に付暇乞也。林一同承る。高橋辰次郎も来。江戸川之儀談す。手負之三木某も来。松前へ賊襲海陸より廻り候に付引揚候段八ッ時頃相分る。手負も多分有之由に付、高龍寺仮病院之儀申遣す。同夜より当病之分為引移候に付、三宅を右へ可差置談事候處不整候に付、高龍寺へ罷越、同人と及談事候處彌以不整。夜中手負共參る。 |
| 5.30 | 十九 | 酒井日記 雨。東風。この日ようやく金華山を越える。 石井略記記述なし 小野日記同断 |
| 5.31 | 二十 | 酒井日記 晴れ。南風。今朝岩城沖。 石井略記記述なし 小野日記 同廿日 霧。四ッ半頃より晴。今朝深霧に乗じ賊キコナイへ襲来。遊撃隊、額兵隊深手負之者有之。伊庭八郎も手負に而来る。其外手負大勢候に付、高龍寺当病之分五稜郭へ遣す。夕刻賊船五艘と回天及発砲。遠而不当。今日松前引揚之兵と大鳥等之援兵挟み撃ちに仍而キコナイを賊引揚る。 |
| 6.1 | 二十一 | 酒井日記 南風強し。この日進むこと僅かに二里ばかり。 石井略記 同廿一日、我回天艦、蟠龍艦、千代田艦、我陸軍を援けん為敵の四艦と尻内沖に戦ふ。発砲互に数十、夜に入るを以互に引別る。此方面、我一連隊、陸軍隊、遊撃隊、砲兵隊、額兵隊、衝鋒隊、伝習隊、会藩の遊撃隊、右八隊合て千余人也。敵海陸合て壱万余と言。
小野日記 同廿一日 晴。總督被參。永井玄頭、中島等来。砲兵頭関廣衛門沓之儀及談判。 |
| 6.2 | 二十二 | 酒井日記 曇り。午下南風雨強く嵐。終夜止まることなく船は動揺する。殊に甚だしきは退くこと二十里ばかり。 石井略記 同廿二日、有川村の方面戦不利にして遂に敗走す。此方面敗すれはニ股口も守る不能、遺憾と雖止を得す遂に引揚る。然るに敵、我厳整なるを見て敢て尾撃せす。故一人も損せす。又寡を以大敵に当り動かさるは是土方君の力也。松前方面の戦也。予出兵せす故に詳に知す、只報知を記す而已也。
小野日記 同廿二日 曇。折々小雨。遊撃隊引揚五稜郭へ来る由。三宅来。明日乗船に付為暇乞。夜中同所へ為暇乞出る留守也。 |
| 6.3 | 二十三 | 酒井日記 曇り。北風波高し。船大いに進む。 石井略記記述なし 小野日記 同廿三日 晴。朝、岡崎へ參りに三宅へ為暇乞參る。高龍寺へ立寄、午刻帰る。朝、木村来る。乗船帰り之儀申談。夕刻又々来而弥乗船に決定之旨にて金子五圓借用之儀申談差遣す。 |
| 6.4 | 二十四 | 酒井日記 曇り。北風。今朝銚子を越え、房州沖に至る。 石井略記 同廿四目、敵の五艦進元函館の砲台に迫る。巨砲八十斤、及ひ廿四斤合て七門を以て烈戦、是を防く。我回天、蟠龍、千代田形、三艦又進む。互に隔つ事拾丁にして烈く砲戦す、勝負を決せす十二字敵艦退く。亦午後進来て互に発砲数百発にして又勝敗分たす、四字比敵艦引退く。此戦、我艦中に敵弾入る事ニつ。死傷四、五名、又市中に男女死傷する数人也。実に憐むベし。砲台に落る三、四発死傷無し。亦我軍の弾敵艦をうがつ四、五発也、甲鉄艦の巨弾丸を見るに長さ三尺にして丸さ二尺余、是を運転する十人力にして用ゆ。其発放に蒸気の機関を以て運転す、故に一時間三発也と言。此艦に及砲、メリケンより渡来する所の物にして日本一と言。此弾丸破裂する其の音天地も震動す。
小野日記 同廿四日 朝少々霧之模様有。後快晴。払暁大砲二発之合図有り。五ッ時過より賊船春日丸を主船にてストンゴール、加賀守其外二艘合五艘にて、向地富川、有川之方より漕来。依而、回天、蟠龍、千代田之三艘台場辺ん位迄漕出、五ッ半頃より発砲相始り、互に打合候得共遠而不当。回天始打ながら少々ずつ台場内へ漕ぎ入る。五艘繰懸りに進寄る。台場にては発砲見合居り矢比見合。四ッ時頃より賊船を打、賊船も五艘にて繰替にし進来る。四ッ時過頃より発砲甚しく、同時頃、台場を打候弾丸病院新建後之荒物屋へ打込、右屋之妻之右足を大に破るされとも骨に不懸。蒲団之積置中へ丸打込已に煙り揚り候得共、近隣打寄消留る。同刻病院屋上を弾丸走り右上之■屋に屋脇之右へ当り石を粉にし而弾丸も破る。右屋之脇板を三ヶ所打かすり丸半に屋中へ弾丸入。此時に当而焼弾丸来候と而、病人とも騒立、一時騒然たりと雖、制止して騒動を休。四ッ半過迄戦甚しくし而、五艘共に有川方へ漕寄、暫時戦止。九ッ半頃有川之方より向岸之方へ寄五艘漕来。繰替頻りに発砲。回天始台場内東へ懸り応砲。賊船進来を引受台場よりも頻りに打出す。賊ふた廻り繰替、春日丸を始とし而、向岸へ寄追々退く。春日丸其外へ手負候様子に見ゆ。八ッ半時頃也。後にホルタンフヘイ来而、春日丸へ台場と回天より打込侯は十弾丸程ストンゴールへ、一発加賀守へも当り候ならんと云。回天台場共手負なし。回天へ三ッ計玉を受候得共、障に不成と也。尤愉快之事にて有之也。○溜町由松妻始母子弾丸に当り、裏町にて弾丸に当りし帰人とも三人並向地よりかつぎ来居候。柏五郎も来。大に取込也。同時異人両人も亜館へ移る。柏五郎ハ左之足首より折切れ、出血始而玄関え来たる時人事なし。続而死去す。 ○三宅大學来る居所を頼。竹中殿も来る。一同乗船に極而引取る ○今日早朝より二股にも戦有りと云。暮合、手負四人来る。 |
| 6.5 | 二十五 | 酒井日記 北風強く夜雨。船進みて入港すること能わず。房総の間に徘徊す。 石井略記記述なし
小野日記 同廿五目 東風。曇雨。昼食事後本陣へ金子為受取出る。榎本、川村、高橋に懸合に及ぶ。出懸けに小林鉄助へ及懸合蒲団之儀也。高松氏手負等引受方之儀に付本陣へ出、榎本対州不都合之挨拶有之る。昨暁より二股へ賊打来、頻りに合戦。昼夜之由也。今暁に至り賊勢屈而引退候由。 |
| 6.6 | 二十六 | 酒井日記 晴れ曇り定まらず。午下南風強し。午ころ小船に移り夕刻横浜脇村え上陸。潜居。 石井略記 同廿六日、敵の数艦来進して互に発砲す数十にして勝敗を決して退去す。
小野日記 同廿六日 雨。五稜郭病院より手負人来候節之儀に付、手紙遣す。夜中牧野主計、松平太郎より之頼談にて、榎對不都合之挨拶方に付、手負人入之儀為談事来る。石井略記 同廿八日の記述より 同廿六日よリ三日昼夜戦ひ死傷尤多し。 |
| 6.7 | 二十七 | 酒井日記 曇り。午後雨。滞留。夕刻事有り。 石井略記 同廿七日、敵茂辺治村に海陸共に迫る。我三艦陸軍を助けんが為敵の五艦と戦ふ、然るに我陸不利にして有川村に退き守る。海軍は勝敗を分たすして互に退艦す。
小野日記 同廿七日 晴。横地秀之丞、榎本對より之頼に付為懸合来。夕、高龍寺へ廻る。夜十二時頃弁天町弁天脇より出火。追々及大火、高龍寺へ焼寄候模様に相見候に付罷越、夫々及差図一旦心配いたし候處、幸にして遁る。鎮火に趣彌無滞を見留、二度目鶏嗚に至而帰る。○亜・英・佛之船共入港。夕に至り退帆。 ○大山酒昨日買入今日より用。 |
| 6.8 | 二十八 | 酒井日記 [松平定敬東京着] 雲立ち。舟行密に東京に至り潜居。 注:坂井日記以下略 石井略記 同廿八日、敵又海陸軍を以て襲来す。我軍、戦毎に不利にして退き亀田新田と七重浜とを守る。同廿六日よリ三日昼夜戦ひ死傷尤多し。
小野日記 同廿八日 晴折々曇。横地より之使に■来。昼後終、横地来。病院金子之儀、蒲団等可為渡候間以来。手負人有之候とも入院之儀、榎對より得頼候趣にて来る。岡崎来る。高橋辰次郎湯之川へ湯治に越度旨に付、柏崎へ手紙遣す。 |
| 6.9 | 二十九 |
石井略記 同廿九日暁天、千代田形番兵艦たり誤て弁天岬の洲に乗り、出す不能止を得す器械を投し艦を捨て小舟に乗し上陸す。故に艦自ら軽し。流に随ひ敵艦に近く、然るに敵襲ひ来ると疑ひ頻に発砲すると雖、千代形より応撃せす。故に敵艦近て見るに人無し、故に奪ひ去る。後、此艦将其顔なきを恥ち死を乞、許さす獄に入る。副将某、自服して死と言。艦寡を以又此如き事、ああ実に時の至らされは也と歎息する而已、此日第二字比、新選組にて有川邑進撃す可きとの令あり。故に所々番兵を速に引揚出陣す。
小野日記 同廿九日 薄暮東風。朝、敵船六艘矢来ないえ取懸、海陸より進来る。烈敷進船より大砲にて打立候に付、胸壁難保。衝鋒隊手負討死多く、諸隊追々引揚。午頃に至而、船を有川之沖へ漕寄候に付、心能罷在り候處、はたして右場所迄敵進来。諏訪手負にて来る。高龍寺へ間席頼に昼後參る途にて、フリウーネに逢。此夜柴来る。昼榎對馬之返事且泉州より之口上申す。ヲロシャえ病院警衛之儀頼可申旨も談す。鶏鳴也。暮より益曇り暗黒也。千代田形過而、暗■へ懸かり候に付破り而、乗り捨てる。亀田新道に至り諸隊と合せ勢を揃ふ。当隊は先鋒たり。彰義隊、遊撃隊、陸軍隊、伝習隊、右五隊合て人員二百人也。大鳥氏是を引率し夜十二字速に進撃す。敵七重浜に百余人屯す。直に我隊進て少く戦、敵忽散乱し有川村民家に放火して走る。我軍連喊して進む。有川に近く数歩にして引揚る。此有川村は海岸の平地にして更に要地無し、我軍此に深く入る。 敵海軍を以て横撃せは進退難きを以て也、故に退て又七重浜亀田新道へ守兵を設け各隊引退く。当隊は一度五稜郭に行、隊を整ひ又函館に帰陣す。 此時我隊、手負二人、戦死一人也。敵の屍十二人を捕ひ、又夫人足十二を捕ふ。且分捕る所の物四斤砲前車付一門、並弾薬少く有リ。 ○此夜敵へ夜討ち之手筈に候處備固くして不能。 |
| 1869年 | 明治二年五月 小 | |
| 6.10 | 朔日 | 石井略記記述無し
小野日記 五月朔日 曇折々小雨。○戦無之八ッ半頃高橋弥吉よりロッシヤ承知之旨申来候得共趣意篤と不分候に付承るに本陣へ出候得共川村留守に付不分夜に入又々出而承る夜半古屋来る今夜七重濱進撃之筈之旨也。二日早天新撰組津田某も少々手負也。七重濱敵追退け候旨也。 |
| 6.11 | 二 | 石井略記 五月仲夏二日、敵艦襲来す。
砲台より放砲せんとする。然に何人の為か備砲尽く、火門に釘を打ち発する不能、一同大に驚き唯周章する而已。然れ共種々術を尽し漸く六門共に発撃するを得たり。此時心中実に悦吾に堪さる也、是より烈戦す。彼我大砲を故つ尤烈と雖亦少々利有。敵艦隊に引退く。
小野日記 同二日 晴。朝食後、岡崎氏相頼魯国マレンタ方へ病院護衛之頼且護衛方仕様相尋ねどして罷越。四ッ半時帰る。五ッ半時過頃より四ッ半頃迄二艘台場にて五艘引受砲戦也。ストンコール、芸州之船へ弾丸当たるいつれも漕戻す。昼、結城■来る。柏崎も来る。柴も同断。前両人に酒食。間宮魯三郎怪有にして脱し来る入院。六ッ過頃より井上、林、柴等来る。情態を歎息して談す。続而、金子来る。酒為給候。敵夜柝を心配す。戦畢て(おわって)是を糺すに砲兵の内に怪しき者あり忽顕れ遂に東風泊に於て梟首せしむ。此者元松前藩にして、全く間者也、実に恐る可し。 |
| 6.12 | 三 | 石井略記記述無し
小野日記 同三日 折々雨。午後、台場より発砲数馨に付及見分候處不相分。仍而、山瀬泊え賊船寄候哉に相聞候に付、同所へ物見に出る。承り候得は三本帆船来候故砲発之由に候得共、最早不相分。本陣へ金受取に木下氏出る。此夜、遊撃隊七重濱に夜討。衝鋒隊に而大川之賊へ夜撃候處いつれも勝利也。 |
| 6.13 | 四 | 石井略記記述無し
小野日記 同四日 晴。四ッ前頃より、賊五艘に而繰懸りに漕来る。回天並に台場を目懸、頻りに戦。蟠龍はかま損し手入中に付不動。四ッ半過頃にして砲戦終り、賊船退く。午半頃、賊船又々進入之様子に候得共不来。程経而台場に而数発発砲す。不審に候處跡にて承り候得は、怪者入候哉にて台場砲門へ釘を打置候者有。之漸々にして一二挺を以賊を打砲す。高龍寺へ參る。 |
| 6.14 | 五 | 石井略記記述無し
小野日記 同五日 東風。大雨。回天あんしやうに懸る。夕刻に至而漸はつる高龍寺へ參る。暮、柴、板倉来、酒食。昼、馬嶋来、酒食。 |
| 6.15 | 六 | 石井略記記述無し
小野日記 同六日 雨。葡萄酒之儀心配候處壱樽相求。會計より百金受取る。
|
| 6.16 | 七 | 石井略記 同七日、敵の五艦、甲鉄艦(天朝)、春日艦(薩州)、陽春艦(秋田)、丁卯艦(長州)、朝陽艦(元旧幕府の艦なり)、暁侵して進来す。我蟠龍艦、先の戦ひに「ケートル」を傷め未だ修復中にして今日運転する不能。敵回天艦を狙撃する連発、回天死カを尽して奮戦すと雖、敵艦五、我艦は回天而已。衆寡は固り敵せす。且敵砲台を去る遠し。発砲すと雖達する能す。ただ切歯扼腕する而已。互に大砲を連発す、其音天地震動するかと疑也。敵の巨弾回天艦を貫数十発蜂巣の如し。且甲鉄艦の二百斤回天の車軸を砕く。故に運転自在ならす遂に沖ノ口番所前の浅瀬に入る、尚屈せす応撃す。其形恰も海城の如し、是を称して鬼回天と言。亦我巨弾敵艦を貫く数十、彼我死傷多し。第三字此敵艦退去す、回天の働き実に称す可也。
小野日記 同七日 晴。五ッ時前より、春日丸、ストンコール、朝陽丸深漕来大戦争。台場へは外二艘に而取掛。五ッ午前頃、回天艦車軸へ当り候に付無拠浅場へ乗上る。発砲春日、朝陽に而益入込打砲。ストンコールより頻りに発砲。右三艘も数多手負。四ッ半前頃に至而、春日退始に而いつれも有川沖へ退艦す。病院高龍寺へも飛丸来り。其外所々え玉来る。丸〆一家火燃上り候得共消留る。回天、蟠龍怪我人二拾九人入院之事。台場にて怪我人無之。過日砲門共え釘打候者砲兵取締に有之白状之上両人斬首。山瀬泊え梟首之由。敵と内意之所行に有之候由。新撰組にて山上え地雷火様之もの仕懸候を、五人召捕候由。高龍寺(より)来る歎願候に付、運上所並に相馬主計、大野右仲方へ罷越、高龍寺へも參り、右一件談事相整。七ッ半前頃帰る。今日戦争回天之奮発、感に余有り。討死五人と云。内、塚本録介(以下欠)。 |
| 6.17 | 八 | 石井略記記述無し
小野日記 同八日 朝薄曇。四ッ頃より晴。五ッ時頃より、大川に当り戦争始る。右手負人六拾名程来る。本陣、運上所、高龍寺へ參る。同寺納金之儀相調ふ。 |
| 6.18 | 九 | 石井略記記述無し
小野日記 同九日 晴。戦なし。玄頭(永井尚志)被參。土方、畠山等来。 |
| 6.19 | 十 | 石井略記記述無し
小野日記 同十日 東風。朝曇四ッ頃右晴。 |
| 6.20 | 十一 | 石井略記 同十一日、官軍海陸大挙来て函館を侵す已にして而。砲声霹雷(へきらい)の如く海上を轟す。砲台に登て見れは天未た明す只火光を見艦を見す。直に海涯の諸守を厳にす。函館港の前面を守る者伝習士官二小隊、尻沢辺村を守る者砲兵半小隊、三本川を守る者新選組半小隊、森常吉新選組一小隊を率て而砲台に屯す。砲兵に小隊、関広右エ門是を率て又屯す。堤上に備数砲八十斤及に、十四斤尤大に堆つ。函館奉行永井玄蕃、砲台の総督と為し協力して而戦ふ。
小野日記 同十一日 晴。[官軍一気に函館上陸支配] 暁より山瀬泊へ二艘、七重濱沖之方より二艘、シリサワヘ之方へ三艘にて、陸地よりは五稜郭へ迫り、早朝後、之方より上陸直に山手へ登り、山上より発砲相迫り、諸方之砲声頻る盛也。依而、病者心配。かねて約し置候マレンタ之方へ罷越、相頼呉候様歎願に付、即刻罷出、相頼帰路猶不動之前に而、官軍に出逢い縛に附き鳥井下に一時余居る。従夫、見合帰る。其時頃也、頻りに戦盛に朝陽も蟠龍之(弾)丸にて沈没。帰り以前、病院へも官軍入来都而、談判済に相成居る。高龍寺も同断。寛大之御所置に候處、最初は津軽藩入込、十数人を殺害。其節木下も逢殺害。赤城一旦被縛候得共聞分縛を解く。其内薩州藩衆入来、彼藩暴挙を止むる之由。回天丸より山上之官軍を打、自焼して上陸、蟠龍丸にて頻りに戦。夕刻に至り、自焼して台場に引揚る。台場外二ヶ所に火之手揚る。高龍寺も近■之處前之方にて防留、其内、沖ノ口方より又々火之手揚る、初は火先宜様に候處、又々東風甚敷相成、終に類焼す。仍而、手負人共不残病院へ為引退候。海陸戦殊に甚し。我海軍は只蟠龍一艦而已、敵は八艦也。湊後前大森浜に向者延年艦と為す、砲台に向者陽春艦(秋田なり)と為す。頻に東風泊に砲し斜に砲台に放つ者春日艦(薩州なり)と為、七重浜の陸戦を援け或は楫(かじ)を転して蟠龍艦に対する者電龍艦(佐賀なり)、と朝陽艦(元幕府の艦今官艦となる)と為す。三本川に向者飛龍艦(長州なり)と豊安艦と為す。独り甲鉄艦(官艦洋名ストンモールと言)、湾中央に来り隠然として動かす。 百五十斤を以蟠龍艦に砲し三百斤を以て砲台に放つ。諸方に於て頻に砲戦寸時も止むなし、其音山岳の崩が如し、海中砲姻漲り艦を見ざる也。両軍雌雄未た知る可す、三本川に向。飛龍艦、豊安艦の二艦、小舟数十散布し陸兵を乗して上陸せんとす。 我守兵半小隊必死防戦すと雖、衆寡相敵せす。右を防がんとすれは左に迫り我軍殆と危く忽にして千余人上陸す(官軍嘗て此の辺海中英国をして測量すと云う)。砲台にては是を知さる也。山嶺に小銃の音あり、仰て見は敵忽然として臥牛山に登、三本ノ守兵を撃す。守兵奮戦すと雖数人して数百に当り難し。況や地理亦失す、遂に敗して砲台に退く。 爰於籠砲す。前面より伝習士官隊滝川充太郎率て七面山に登砲撃、須庾(しゅゆ)して死傷多く援兵無を以遂に五稜郭に退く。 敵忽踵下、一は則函館と五稜郭の道を絶つ、一は則砲台を襲ふ。砲台の諸隊火を柵外の民家に故つ、炎煙天に漲り恰も白昼の如く而防戦尤勉む。 敵艦四方に向ふ者皆湾中に集る。我蟠龍艦、敵の数艦砲台と相応して而戦ふ、其砲敵の朝陽艦の弾薬庫を砕く。薬発して艦忽粉砕沈没して一塵無し、其音海に轟き千雷の如し。炎煙天に満、艦中の数兵空に飛ひ海中に没す。生て岸に達する者僅而已、我軍皆快と呼、諸長大に喝て曰、 此機失ふ可らす、 兵大に奮ふ。蟠龍は猶敵の数艦と死を決、鼓勇東進西馳戦ふと雖、弾数十を受遂に運転する不能。岸に依り台場と為して以戦ふ。弾丸既尽るを以て小舟に乗し艦自焼て皆砲台に入る。此艦の副将松平時之介、艦上令す。甲鉄の百五十斤其胴を狙撃す、体粉砕飛て一塵無し。艦将松岡盤吾、海軍の術に熟練、艦を回らす我手足を使か如し、故に一艦を以て八艦に敵す、実に称す可也。回天は先の戦ひに損し今日運転する不能、是又台場と為して戦ひ遂に五稜郭に退く。此戦や海軍の巧み戦尤多と雖、遂にニ艦共戦ふ可。爰に於海軍の戦ひ止む。 然れとも陸軍の戦ひ猶烈し、砲台籠郭に方るの時、陸軍奉行添役大野氏、援兵を乞ん為五稜郭に行彼後砲台に帰るの日、我五稜郭の状を詳に問、彼曰、 千代岡に至り新選組の長兼陸軍奉行土方歳三君に逢ひ、彼砲兵二小隊を率而将に砲台を援けんとす。 吾も亦馬首を回し従て而、共に一本木の街柵に至る。士官隊是に揚来り吾を呼て曰、戦ひ七面山支る能すして而退く、且吾傷す又戦ふ可す。今日既迫る吾隊君に託す故に惰なる者在らは則請君斬れ。 面色赭(あか)の如く眼光人を射る、血流て韈(たび)赤し、蓋し士官隊長滝川充太郎也。時に士官隊と合て而速に進む、然れ共敗兵戦成難く、土方君曰、吾此柵に在て退く者を斬る。 吾に兵を率而戦ひ敵勝に乗し銃を放ち戦挑む。額兵隊をして市街の左に進め、士官隊をして海涯と市街に散布して而進む。敵始少く動く。士官隊銃戦を巧して而戦ひ、且進て銃を投て白刀を抜き身を踊て而進み刀闘す。然るに後を守る額兵隊惰して進ます隊伍乱す、敵の尻沢辺を過るを見て而喧ふ敵我後を断つと伝。吾叱咤一歩進は則十歩退く、勢ひ制す可す。吾思ふ、奉行土方君必是を柵に留んと欲するに皆柵を過て而行く。吾奉行と約す、被が如して而留さる者何ぞや、遂に千代ヶ岡に退く。[土方歳三死す] 陸軍奉行添役大嶋虎雄、安冨才介に逢ふ、被曰、 奉行土方君、馬を跨柵の側に在り、敵の狙撃する処と為て死すと告ぐ。
我悲歎、直馬を馳せて五稜郭に至り総裁榎本君逢ひ審に函館の敗を語る。榎本君曰、新選組、砲兵のに隊砲台に囲るると知て而是を救はるれは則不信也。何を以諸隊に令せん、吾自進んて救んと既馬に鞭んとす。 皆馬を叩ひ諌て曰、総裁砲台に向は則他の方面を如何せん、総裁此座動く可す。 副総裁松平君(太郎)曰、吾総裁に代て進み戦ん。 駿馬に鞭打千代ヶ岡に至る諸軍に令す。海涯の沙山を環り進む者額兵隊と見国隊也。士官隊は本道を進み榊木隊は人員少く、且其長酒井良祐、鍬ヶ崎の戦に死す。故に士官隊に合て而進む。敵既一本木の街に陣し柵の間に兵を散て侍つ。両軍合兵し、且集り且散し且侵且支ひ起て而銃を放つ者在り臥て放つ者有り、或は小隊銃を放し、或は大隊の令を下し戦ひ数刻に及ひ勝敗を決す不能、我軍退く。敵亦敢て進す。諸隊皆千代ヶ岡に集る。見国隊長に関源二死す。屍来る。額兵隊長星恂太郎、剣を抜ち嘆日、 我隊甚惰也、諸君を視るに面目なし。 彰義隊々長渋沢誠一郎、蓬髪覆面意色甚悪し、遊撃隊長柏崎才一黙して而答す、独り千代ヶ岡総督中嶋三郎之介、年六十余「髭」髪眉半白、申を以て傷を給し意気従容して曰、吾是岡死する而已夕陽西に傾く。副総裁千代ヶ岡の守を厳して而五稜郭に帰る。吾又従て行。後中嶋氏父三人、千代ヶ岡将に敗せんと欲る時、堤上に登り白刀を抜き大声を発し大軍に斬込、父子共に死す。其勇気憾するに余有り。
此日戦、五稜郭西南に郊る者、伝習歩兵隊、一連隊、遊撃隊、工兵隊、衝鋒隊、春日隊也。暁天より勇を奮て戦ふ、亦鋒を鋭而侵す、大小銃砲を放つ瞬息の間も止むなし。殺傷頻多し、日暮両軍止戦、河を隔て塁に対して陣を取る。我諸隊に令る者陸軍奉行大鳥圭介、及れしめん隊長本多幸七郎也。伝習歩兵隊率る者大川正二郎也、一連隊を率る者松岡四郎次郎也、遊撃隊を率る者沢録四郎也、工兵隊を率る者吉沢勇四郎也、衝鋒隊長古屋作左エ門死す、春日隊長春日左エ門死す、此時五稜郭を守る者凡九百人斗、千代ヶ岡を守る者四百人と言也。時に函館の砲台を守る二百人、五稜郭と砲台と遮る所と成り声息通る不能孤立して戦ふ。
○大小は除医師外之器械大小不残相納。 |
| 6.21 | 十二 | 石井略記 同十二日、砲台終日銃戦烈しと雖、勝敗を決せす。
小野日記 同十二日 高龍寺入来御手当取計、今日も台場敵船等にて砲戦有り。時計所持之分不残可納旨に付取上に成る。夜半頃、薩州隊長池田次郎兵衛、村橋直衛其外四五名諏訪方へ来り、五稜郭並弁天台場恭順之趣意にて、種々談判帰り候上高松氏拙者へ諏訪より意を承る。三木、洒井、木村へも申談。五稜郭並台場へ使可遣外無之に決定す。鶏鳴過ぎ也。 |
| 6.22 | 十三 | 石井略記 同十三日暁、敵海陸大挙来て砲台の柵外に迫り、海陸より大小砲烈放し速に砲台を奪んと知る、其勢ひ破竹の如し。砲声霹雷の如し。我軍少なりと雖海涯に突出し巨砲を備へ、尤要衝に当り守を厳にして鼎峙の勢を為す。敵軍から以敗り難きを知り黄昏退く。
小野日記 同十三日 晴。五稜郭、弁天崎御台場へも草案認為持遣候處、少し書加に而、先ッ御台場計へ可遣旨にて返事遣す。仍而、彰義(隊)手負人高橋與四郎、一聯隊手負伊南誠一郎相頼、御台場へ遣候處返事来。右に付薩藩永山来て、五稜郭へも直に使節可遣旨に付、伊南、高橋文四郎可遣之處、高橋は重手之身にて痛候に付、回天丸乗組坂脇杢之丞頼遣す。最早暮方に參る。明日昼後七字迄挨拶有之度旨之機限にて出る。今日も戦有り。村橋、永山氏度々其外入来之事。是の台や明砲の厳なる事至らさる所なしと雖、唯一つの誤りあり。故は小井一つにして要水に乏し、是築たる人の誤也。故に籠郭の時に方に大に水を貯つと雖、嗚呼不幸成乎、先の戦ひに海軍の巨弾其水器を砕り今日水つき、米あれとも焚不能、傷者の疵洗ふ能す。憐むべきは乗馬也。水無して終死す、兵又其肉を食ふ。古にも水道を絶れ苦む事有りと知。 今日予既爰に至る、其苦状述難き也。愈各心を一つし必死の勇気益盛也。敵軍死傷多し、力を以て敗る能さるを知り敢之を侵さる也。 |
| 6.23 | 十四 | 石井略記 同十四目、我病院に在所の医高松凌雲、執事小野権之丞より詳に薩藩他田次郎兵衛(官の軍艦)、我傷者諏訪常吉、病床に来て語る所を書し、傷して病院に在る者高橋与四郎、伊奈半二郎をして小舟に乗し白旗を飄し砲台の下に携ひ来らしむ、且官軍の意を伝ふ。其書に曰、諸長議して書を以て答ふ。砲台は支塁也、決す可す、五稜郭に至而議す。
小野日記 同十四日 戦なし。晴。暮過、永山氏帰来り。続而、(五稜郭への使者)坂脇、伊南帰り来。総督並副総督より而名之返書持參。會議所へ差置候由。夜に入、松岡、相馬主殿、大野右仲等五稜郭より帰りに立寄礼申述る。○鶏鳴近に至り、五稜郭総督並副総督より之返書寫に而薩州より送遣。明早朝、永山罷越候間、台場へ右寫を寫取可遣わす旨、尤其節一同永山も台場へ可參旨也。仍而、右寫取、台場へは彰義隊服部安次郎可遣様談事承知に候事。 |
| 6.24 | 十五 | 石井略記記述なし 十四日の記述から 其翌十五日、陸軍奉行副役兼函館市中取締相馬主殿、蟠龍艦将松岡盤吾共に五稜郭に至る。薩藩永山友右エ門(此仁我軍函館を得るの後二番回天艦を捕ふ、永山氏此艦の将たり、捕て既に斬首せんとするを、永井公死を許し藩に返す故に知所の人也、降る時永山友右エ門と言。実名田嶋敬ニと言)自先て令を諸軍に下し行を開く。途永山氏、両氏に謂曰、
小野日記 同十五日 朝曇。[台場和議成る] 暁七ッ半頃より諸船並ストンモールより五稜郭へ向大に発砲す。今昼頃、唯今と申す義にて薩藤岡より手紙に而、医師一人一昨日台場へ參り候由、両人之内壹人会議所へ可參旨申遣候に付、伊南、蓮沼差出候事。右は酒肴を台場へ送る使節に行に付、一同之義に付呼寄候也。今日台場和議成ると云。今日之事実に義戦也、諸藩之を悪者無し諸君限り有るの兵を以て限りなきの天兵に当るは一日勝有と雖其敗るは必せり。且兄弟相殺す、朝廷万国と並ひ立んと欲の深意也、其意説て而和せと欲する者の如し。 相馬、松岡の両氏、総裁榎本君、副総裁松平君に逢ひ高松、小野二氏の贈書を語る。両総裁曰、吾二人亦二子より贈書在りと雖、夫吾等蝦夷地に来る故、昨冬上る所の書に尽す今日に至り言可き無也。吾嘗て歎願する処の旨趣を復歎願し、許容無き時は寧死共謝す可らすと、一つの答書を送る。 総裁曰、答書官軍肯れは則蜂火を挙け、肯るれは則数砲を轟がして以砲台に報すと。議既に定る。 両氏砲台に帰る。永出氏へ又送る。相馬氏、永山氏に謂て曰、榎本、松平、日暮必書を以高松、小野に送る。 二子是をして参謀執事に達せしむ。吾亦答無也。○暮合、村橋来る。台場手負人可遣旨談。 |
| 6.25 | 十六 | 石井略記 其翌十六日、永山氏暁を侵し砲台の柵外に来る。永井公、相馬氏出会す、永山氏曰、
小野日記 同十六日 東風、雨。今日も諸船より五稜郭へ発砲す。昨日よりはゆるやか也。山上へ立退居候町人共追々下住相始る。今日、津軽陣屋落ると云。榎本、松平二君より答ふ処の如き戦ひを止む不能受、再ひ之を思慮せよ 其意懇切信義を以談する者の如し。永井公、相馬姓、河邑姓(録四郎と言)、永山氏をして五稜郭に行両総裁に逢ひ議す。断然して変せす。[官軍永山による降伏説得] 榎本公、永山氏に千代ヶ岡側の橋上に逢はしむ。永山氏説て而降らしめんと欲す。榎本公曰、 官軍吾等を思ふの厚きに感せさるにあらす、然れとも降能さる也。
永山氏亦降色なきを見再ひ説す。三姓榎本公に謂曰、今日総裁意決すれば則砲台の諸長又決す、然れとも五稜郭と砲台と官軍の遮る所と成り声相通せす。
只衆議の宣布処に従ふ、必総裁の命を奉る不能也。三姓並騎て而帰る。永山氏嘆て曰、多殺傷益なし、且海軍外国と交際、朝廷其人に乏し、榎本君の如き実に惜む可き也、吾誠之徹せさるを何如ん互に戦ひを刻して而別る。
日中に当りて官軍酒肉を以砲台諸隊に労す、是則榎本公海軍、皇国無二の書を贈に依也(五稜郭も同じ)。
且言ふ、蜚箭乱弾の中と雖、或は行人を遣り白旗を揮而進者是也、請之を殺傷する勿れ、実に元亀・天正の遺風有り。
此時彼我自相親み軍情少く衰ふ、然れとも各其心を決する処は則毫も動かす。皆官軍贈る処の酒を酌て曰、一酔快戦する而已 既して而、鞭馬来る者有り即永山氏也。砲台の総裁永井玄蕃逢ふ、曲折論談す。永井公、諸隊に謂曰、 我受処を許さすして而直に大軍を以て来侵す、士たるの道、戦はすんはある可す。自思ふ、吾等罪なし然れとも遠く天兵を労すれは則謝せすんは有可す。諸士以て何如と為す。
皆曰、成れは則義名を天下に挙け、成らされは則死は固り期る処也。今日の事既是二至る唯一死有る而已。
永井公論して曰、諸士死を以其身を潔んと欲すと雖、官軍信義を以て語る、又棄つ可らす、且徒に死す益なし、若遇するに士たるの道を以すれは則官軍の意に従んか、
皆首を垂れて答へす。暫く有て曰、僕等患処の者、此膝一たひ屈すれは則刀を帯するを得す、いやしくも刀を帯するを得は余は総裁の命是従ん、自兵器を投して降る四支を寸斬すと雖為す不能。
永井公の和を聴すや五稜郭に在る所の両総裁の如きは、一つ二死を決すと雖、兵隊の如きに至ては将に「モロラン」に脱んとし或両裁の首を携て敵に降るの議あり、軍情大二哀ひ瓦解の後死る不能、又和る能さるを以遂に降るは必せり。永井公、先つて是知り聴す也。永井公曰、永山氏と議す、ニ人相約す、只刀を帯ひ尽く余の兵器上り自恭順して而、天兵を労するを謝す。けだし降るに非る也、又和るに非る也。
日暮れ官軍の軍監参謀の書を奉し砲台に来り、恭順実効三章の令を下す。其書に曰。恭順実効之ケ条
皆不豫の色ありと雖、猶士たるの道を失はさるを以自其心を慰む。然れとも年少血気の士の如き慷慨切歯止む能さる者又有り。
一長官之者陣門へ罷可出事 一願之通台場内に恭順追而、朝裁を相作可申事 一双刀之外兵器悉皆差出可申事 右之通申達候条可得其意者也 五月 海陸参謀 ○台場手負人、拾八人參る。今夜暁過より暁に至り諏訪死去す。暮頃、村橋より一人參り呉候様申来候、伊東罷越候處、先以薩州にて警衛之筈也、都て宜敷取締候様との事也。 ○器械納之分は同人迄心得に可申入旨也。 |
| 6.26 | 十七 | 石井略記 同十七日、五稜郭遂に降に決す。両裁既に屠腹せんとす、皆是を止む。
小野日記 同十七日 東風にて晴。朝少々五稜郭に戦有りと云。終日取調に困却す。暮に至り村橋へ器械納之分相廻す。薬種間違にて当院へ相廻候に付台毫場より申立と相見へ相送遣候事。○諏訪取置相調候。 |
| 6.27 | 十八 | 石井略記 同十八日、官軍の軍監前田某、又砲台の下に来り、降伏謝罪実効二章の令をとす。其書に曰
小野日記 同十八日 曇。[五稜郭落城、榎本武揚降伏す] 五稜郭昨日降伏之由寺師来て告申候。村橋方へ手負人名差出候。終日人別改に困却す。辻好太郎■■之筋有之候に付縛す。謝罪降伏ケ条
且ひそかに論て曰、一長官の者陣門に降伏可致事 一帯兵兵器悉皆可差出事、其余は寺院に於て謹慎罷可有事 五月 海陸参謀 千代ヶ岡既に敗し又稜郭降る。榎本君双刀を上る、諸士双刀を帯すれは則、本支相異也、吾又諸士をして双刀を脱せしむるに忍すと雖、榎本君の為に忍而上れ。
皆見て愕然貌恭して而心怒る。永井公曰、 議を退て而後答ふ、
諸隊大に喧し皆声を変して曰、粟十旬を支るに足る、弾十余戦を為に足る。一勝等無と雖決戦して以身を潔すヘし。
然とも官軍信義を以我に語れは、則我又信義を以応せすんは有る可らす。遂に恭順を為に至る。戦ふと戦はざると、刀を帯と帯さるとに決す、其関する処実に大也。一旦帯刀を許し尽兵器を上らして而後謝罪の令を下す遇に降人の例を以す、何ぞ吾等を児童と見るや。吾等身を蝦夷に十死有り、一生無一片の義に心を安る而已頭断す可き也。刀脱す可らさる也。永井公論曰、始恭順せされは則勿論也、既恭順して而。今軍監の意に逆は則一罪を重する也、且軍監の言其理無に非る也。
諸長皆、永井公の意に従て而説論す。諸隊黙して而答す。永井公及諸長怒て曰、吾等快意双刀を上る、諸子肯ざれは則各其欲る所に従ふ。
皆涙を拭て曰、総督及諸長双刀を上るに僕等上られは則独官軍の意に逆ひ、又総督及諸長の意に逆ふ也。忍て而是を上る、然に世皆僕等、生を愉むと言ふ只遺憾と為す而已。
永井公出て軍監に逢ひ答ふ、謹て謝罪の令を奉し皆双刀を上る。其夕 五稜郭より榎本、松平、大鳥、新井の四君、砲台より永井、相馬、松岡の三君陣内に降り其寺に入る。 此時役、被我戦死する事其数を知らす。我が新選組に死る者栗原仙之介、粕屋十郎、武部銀次郎、永嶋五郎作、津田牛五郎、歩兵祐二郎、傷者谷口四郎兵衛、寺井主税、鳥羽多喜松、五十嵐伊織、角谷糺也。諸隊津軽青森へ行し謹慎す可きの令有り。 ○相馬主殿、森弥一右衛門来。今日五稜郭より手負人送来候得共、席無之旨相答候に付、外へ転す。濱尾最一郎、白岩覚之助、加藤昇平、杉原半治泊す。 |
| 6.28 | 十九 | 石井略記記述なし
小野日記 同十九日 雨。大病院より高松呼出に来。蓮沼、赤城、伊東友賢も出る。川添誠之丞入院。菅野湫水も来。大野内蔵介も来候事、是迄薩州にて取計来候處以来大病院之指揮に可隨旨永山申聞候事。手負人疷(てい)所明細書調に付大取込。 |
| 6.29 | 廿 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿日 晴。糧米之儀に付、薩州村橋方へ手勢遣し受取る。大小■方より可受取旨相分る。遊撃隊隊長より手勢にて数人病人送来。席無之に付外に移す。○湯治に居候病人共数人浄玄寺へ著候由。花岡、濱尾来。山路、小林入院之事。是迄御雇之医師、大病院より沙汰に相成。是迄之通出仕之筈也。 |
| 6.30 | 廿一 | 石井略記 同廿一日、第十時、英国艦(アラビオン)に乗し既に函館を発し五時青森の港着艦す。其夕 濤波荒くして上陸する不能、艦中泊す。
小野日記 同廿一日 曇。暁、御台場並び総督其外上等之分出帆に相成候由。取締手伝江幡徳三郎来り、元会津屋敷仮病院に為渡候間一人可罷越候に付一同罷出候事。高松氏も浄玄寺より直に来りに相成。薩州寺師双眼鏡並びに時計四ッ返しに来る。 |
| 7.1 | 廿二 | 石井略記 同廿二日、上陸して蓮華寺に入り、黄昏新選組油川駅明誓寺に移り謹慎す。警衛厳也。
小野日記 同廿二目 曇。湯之河より不残引払い来候由也。病者快方之者二拾人余出院、称名寺へ移り候事。千代塚始取世話之名義聞済に相成同人坂脇元會津屋敷へ移る。 |
| 7.2 | 廿三 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿三日 曇。折々小雨。明ヶ方大雨。今日九半一升に罷在候病者、元會津屋敷へ引移候様、永山申聞候に付引き移す為、其の両所へ為改め罷り出る。○英医並びに大病院より数人来。当院人員書並人別書取調へ差出す。 |
| 7.3 | 廿四 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿四日 曇。今日薬代四拾一両余受取来る。英医、元会津屋敷並浄玄寺見廻候由。右に付切所可致者彰義隊小宮山彦之丞、額兵隊久太郎両人当院へ移る。十五才以下之者会議所へ同道之事。 |
| 7.4 | 廿五 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿五日 曇。暁より雨。終日東風寒。井上来、藤岡も来候由。風順悪く船損居候に付、過日出帆之船共漕戻し候由咄有之候由之事。 |
| 7.5 | 廿六 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿六日 東風。終日大風雨。別義なし。○七尾酒求。 |
| 7.6 | 廿七 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿七日 雨天。五稜郭より持參之薬籠並安藤精軒薬瓶入之箱見当候旨にて、村井、佐野大病院へ出候節差出候様との事に付為差出候。英医及安藤精軒始医師共来り、病人夫々見舞に及候。額兵隊指図役遠藤良治俄に差迫死去す。 |
| 7.7 | 廿八 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿八日 朝雨。追々模様相直る。昼後天気に成る。官軍蒸気船朝一艘出帆。ストンゴール外二艘昼後蒸汽を焚を見■頃出帆。夕に至り外に一艘出帆すと云々。秋田表に軍始ると聞。青森より帰候町人之咄に、右青森へ秋田表より援兵之儀を櫛の歯を引か如く来ると。右は仙台、會津、庄内辺の脱兵なりと云。筒井助次郎、高橋辰次郎等金無心申越置候に付、称名寺に居る趣に付手紙に而遣わせ候處、礼状遣す。 |
| 7.8 | 廿九 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿九日 晴。金子、並河より高松、蓮沼、赤城へ手紙遣ス。今日も官軍蒸気船出帆すと云々。英医安藤祷軒今日も来る。 |
| 1869年 | 明治二年六月 大 | |
| 7.9 | 朔日 | 石井略記記述なし
小野日記 六月朔日 晴。折々曇。額兵隊、久太郎右之手切断に付、英亜医師深瀬等来る。 |
| 7.10 | 二 | 石井略記記述なし
小野日記 同二日 晴曇不定。東風。ワートル薬性、日本外史其外本類拾二箱、長野昌英方へ差出候。○金子、並河へ手紙差出候處居所不相分。 |
| 7.11 | 三 | 石井略記記述なし
小野日記 同三日 曇。金子、並河居所為相尋候處不相分。井深、称名寺へ移り候由にて手紙遣ス。右寺に柏、柴始居候由申越。諏訪金之儀称名寺より度々申越。柴より廻し置候金並び諏訪薩州より到来二十五両之内二十両相廻す。且ッ間宮所持之分も相廻す。○三石来。岡崎始之居所も相分。 |
| 7.12 | 四 | 石井略記記述なし
小野日記 同四日 曇。昨日度々申越候金之儀入組候に付、称名寺へ赤城出向相頼。間宮、諏訪金之儀に付云々有り。 |
| 7.13 | 五 | 石井略記記述なし
小野日記 同五日 くもり。在住隊教導役関口八郎来る。御台場より入候者、大小可受取旨及談判候へ共、元々御沙汰之次第と齟齬いたし候に付、伺之上ならて難渡旨相断伺書差出。○間宮を称名寺へ送り遣す。 ○両日之内、幸三郎来る。初而金高分る。 |
| 7.14 | 六 | 石井略記記述なし
小野日記 同六日 曇。関口又々来る。大小之儀可受取旨申候へ共、伺之御差図無之に付不渡。井上干城来る。右大小可渡旨會議所之決定也と云。乍去、先御沙汰且病者心得罷在候儀等申述べ候得ば、立帰可及評議其上可及挨拶旨にて帰る。取締富士又八郎来而、右大小之儀段々之次第相咄候に付、次第相分候故可渡旨及答候處、明日九時受取人可差出旨に帰る。○間宮再発之由に而称名寺よ送り遣す。然るに右に居候者より一応之儀不申越甚不審と存候。 |
| 7.15 | 七 | 石井略記記述なし
小野日記 同七日 曇。大小受取関口来候に付、受取書取て相渡す。朝迄間宮之儀申越候哉と相待候得共、何之儀も無之に付、同藩之方へ及発言候次第有之侯事。 |
| 7.16 | 八 | 石井略記記述なし
小野日記 同八日 陰。東風。終日大雨。 |
| 7.17 | 九 | 石井略記 六月九日、弘前行の令有り、明誓寺を発し青森蓮華寺に休し、夜十二時達し薬玉院に入る。此日暴雨、途して晴る。
小野日記 同九日 終日雨東風。 |
| 7.18 | 十 | 石井略記記述なし
小野日記 同十日 陰天雨。■求。 |
| 7.19 | 十一 | 石井略記記述なし
小野日記 同十一日 晴陰不定。木下期日に付、心新也。今暮頃より、高橋友安不居。種々探索。夜中及雨。○三人より金取戻し■を。 |
| 7.20 | 十二 | 石井略記 同十二日、生国役名に及旧藩を書して出す。長く是に慎む。
小野日記 同十二日 天気之模様に成る。乍去、快晴には無之。昨夜、長鯨丸入港之由に付一見す。今日蒸気にて官軍出帆すと云。東條も来候趣傅言有り。蓮■伊之三人へ五十円づゝ相頼。○千代田戻り入。 |
| 7.21 | 十三 | 石井略記記述なし
小野日記 同十三日 陰。赤城、東條方へ朝之内出迎。 |
| 7.22 | 十四 | 石井略記記述なし
小野日記 同十四日 晴。古屋氏今朝死去。井上干城両度来る。医師姓名書差出候様之聞。○昨日両人死罪之者有之右布告書来る。 |
| 7.23 | 十五 | 石井略記記述なし
小野日記 同十五日 晴。今夜、金箱食事之間に紛失。夜中種々探索且手配等いたす。 |
| 7.24 | 十六 | 石井略記記述なし
小野日記 同十六日 雨。早朝、昨夜之業人相分。看病人栄吉親分へ引渡。鶴吉、亀吉へ褒美遣す。 |
| 7.25 | 十七 | 石井略記記述なし
小野日記 同十七日 曇。折々小雨。 |
| 7.26 | 十八 | 石井略記記述なし
小野日記 同十八日 晴。 |
| 7.27 | 十九 | 石井略記記述なし
小野日記 同十九日 曇。快気之者二拾一人出院。寺沢兵衛来。医師是迄之進退之次第並びに当院畳数を問に付、書出す。○スネール之弟来る。今夕、英之帆前船コーショウ艦にて二三百人横演へ向出帆に可成と云。 |
| 7.28 | 廿 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿日 曇。晴之事と有り。今日、降伏人之内、長鯨其外之者共百人程免許に成と云。回天義三郎蟠龍年太郎等礼に来る。受人を得御暇戴き候と云。近々長鯨出帆に可成と云。 |
| 7.29 | 廿一 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿一日 曇。四ッ過頃英之帆前船日本印を揚出帆。○夕、英船入港。 |
| 7.30 | 廿二 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿二日 昼前中晴。後雨。高松、長野昌英より呼出来。病院掛りは彼より可廻旨申す。昼後、富士亦八郎来而、弥右之儀申談、浄玄寺、元会津屋敷共に同断之旨申す。仍て、諸帳記勘定書等引渡候處、守衛之者無之、其内俗事取締申付られ候旨にて渡辺関蔵来。松前藩之由也。右へ引取方申談候處不相分。高松より申談候得ば取締へ出候序有之候間承り可申旨に付、帰りを相待居候内、夜六ッ半過に至り同人帰る。猶、沙汰可致候に付夫迄先ッ是迄之通にて居候様との事也。仍て、先ッ其夜は同所安眠す。○手負当病軽重之次第生國年齢今日中に可差出而尤元會津屋敷、能量寺共に同断之事也。夜半過迄に取調差出候事。 |
| 7.31 | 廿三 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿三日 雨。今日より守衛兵昼夜四人づつ相詰候様相成る。新兵隊之趣にて来る。○會議所より高松氏呼出に来。佐野噂其外之用事也。 ○佐野は降伏人之内不入様に和成る拙子守衛兵従是可相廻旨申候由に付今哉々々と相待居る。 ○今日元會津屋敷、浄玄寺掛り之者引移候由也。 |
| 8.1 | 廿四 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿四日 晴。今日も何之沙汰無之。先ッ其通に相勤居る。三拾三人出院に成る。寺沢来る。医師生國先役名当地へ来候而は何役相勤候と申儀可書出旨申に付、拙者も其砌(みぎり)一同書出候事。○柴、柏崎方より配分金相廻候事間宮分も相廻候に付直に相渡。 ○夜に入、寺沢又々来。病者共に生國役名等医師之通に可書出旨申に付手下いたし病者共に不残承届書入遣候處、鶏鳴近に相成る。 ○高松長野へ出候處、明日病院不残引渡に可相成旨咄有之候に付、昼後より心掛いたし候。暮合に至り関蔵を以、取締より其儀申越。是迄残米之分百■人へ今明日と割渡。 |
| 8.2 | 廿五 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿五日 曇。昼後より晴。引越候付大混雑也。富士亦八郎昼後来。病者引越八ッ半頃迄相済。跡取片付在来之諸帳記旧帳台結通帳之類一結、高松名に而、長野昌英方へ送遣し勝手働は相残し、洗濯女親子も同断小使並看病人は不残引連病院は日野■。右両人へ引渡暮に而元會津屋敷へ引移申候事。 |
| 8.3 | 廿六 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿六日 曇。折々小雨。松前藩隊長何々辺逢度旨に付及面會候處、病院掛にも無之、病者にも無之、如何様之次第にて当方へ參候哉之尋有之候に付、先より懸入候様相咄御沙汰を相侍罷在候旨相伺候得は、其旨取締へ可申述旨に而相分る。無程取締へ相伺候處、弁天崎御台場へ罷越謹慎可罷在旨に付承知。高松に諸帳記金銭等引渡守衛護送を得、七ッ時以前頃、弁天崎御台場へ入る。居所を守衛人より差図して、是迄居候、見国隊小頭平間恒治と申之由跡にて承る。右居所を下け其所に可居旨申聞一同之者傅習隊中嶋與七、同士官隊大野俊二郎、遊撃隊山口寅吉、彰義隊山本徳次郎、海軍隊鳥山三郎も右に続而可居旨也。守衛人退候て席談少々有之。右居所■寝場之如し人間の住すべきにあらず。右小頭周旋して、居所を別梁士官之居候處へ談呉候に付右へ引移山田氏居る外に高橋浅之丞、岡本潤馬、田中兼次郎、加藤八十二等之者並びに見国隊之者之属所へ割込。其夜明ヶ。 |
| 8.4 | 廿七 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿七日 天気。姓名調に両度来。夜に入、明日入艦に候間四ッ時迄に揃置候様と之傅也。但、士官計。○下役に頼品々相求。 |
| 8.5 | 廿八 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿八日 天気。[函館から東京へ移送に] 早朝、蓮沼、赤城之内診察之儀願申立候に付、赤城来る。仍而、高松始■傅言相頼込、此間相廻呉候五両二分合而、諏訪之金子■両三分実行寺へ遣置呉候様相頼、右に付赤城心配いたし呉金子之儀、若赤城存意通に相成候はば諏訪之金へ合可呉旨、相頼相則。昼後、早速に乗船候而なお又傅有之候に付役相頼遣候處、承知之返事来。昼食無程、相揃著替等手自持參出起内溜運上所脇へ扣(ひかえ)同所に而称名寺に居候同士と一見之上、遠方より一礼無程、阿州之戊辰丸へ順々に乗組。警衛は備後福山賄は備前之手也。箱館港七ッ時過出帆。海上大に和き波平也。暮に津軽海之沖へ出。夜中も波平也。沖を漕ぎ候故歟(か)、もやにて山一切不見。 |
| 8.6 | 廿九 | 石井略記記述なし
小野日記 同廿九日 天気。無事にして航。 |
| 8.7 | 晦日 | 石井略記記述なし
小野日記 同晦日 天気。朝、松魚漁舟大出居候に付、山は不見候得共、荒濱或は相馬沖辺ならんと云。 |
| 1869年 | 明治二年七月 小 | |
| 8.8 | 朔日 | 石井略記記述なし
小野日記 七月朔日 山一切不見航す。夜半過に至り一時間程風来雨。 |
| 8.9 | 二 | 石井略記記述なし
小野日記 同二日 晴。折々雨。午時頃犬房ヶ崎を過、暮に房之洲之崎を漕入ると存候處不入。 |
| 8.10 | 三 | 石井略記記述なし
小野日記 同三日 北風。天気。洲之崎を不入して大嶋々山舟先に見る。承れは夜中故、舟を不入由也。八ッ半過頃、品川沖へ著岸す。風度々替わり、昨宵より船中炎熱如焼、不堪困居、かん板へ出而、衆皆凌炎。明日は上陸也。用意之儀守衛より傅有之。 |
| 8.11 | 四 | 石井略記記述なし
小野日記 同四日 晴。朝もやに而、品川聢(しか)と不分。五ッ過頃、守衛船漕来候に付、皆上陸用意す。五ッ半頃乗船品川濱手柵木之有之空地へ衆を溜め、跡船之漕来を待合す。日陰なく炎天に困却す。皆々上陸之上、品川願成寺へ備前之護送に而、四半前入寺。四百五十人一同也。船中の可比に非されとも、大勢故悉雑倒す。始て人之住むべき所へ入候心地也。船中見國隊と雑居候處、右隊出張も永く引続き御台場厩如き所に凌し人々なれは、所謂甲冑キシヅを生し、衣類虱(しらみ)連行故、枕を並へ而伏せは、虱頻りに飛込み覚有之而、則蛇カッの恐れをなしいとゝ眠得す。入寺之上点検すれはゲット虱横行犢(とくに)ビコンえ巣窟をなし剰蚕マイをはがす時之如し。爾後、東嶽奇逸楼等扇面へ書画を数多染筆頗る終日之積屈を伸ん心地也。明日は又宮津侯之許へ御預ケと云。居所はいつれ之所か不分。 |
| 8.12 | 五 | 石井略記記述なし
小野日記 同五日 払暁より雨。今日は引移に付、雨具心配之處御渡可相成と云。足草わらじ渡に成る。八字頃出起。矢張、備前之護衛也。英式調練にて前後を衛、赤羽へ出、増上寺之内へ著。四ッ半過頃也。四百五十人門内へ繰込せ、同所に而は親兵と備前にて人頭受取渡有之。備前兵退て、五拾八人当院■■寮へ分配に而入。蒲団壹人に付壹枚づつ、蚊帳壱四張り御借渡に成る。風呂も立て被下、食料も是までに無之程丁寧に被成下。御親兵之咄山田承り候處左之如し。箱館降伏後、薩長十萬石づつ御加増、土佐三萬石、彦根大柿同断。御二家壹萬五千石づつ也と云々。
○扨今日、同行之者当寺之分三ヶ所に分ると云。御守衛は御親兵に百貳人づつ詰合警備す。午後天気。夕地震。 |
注:石井見聞略記および小野日記以下省略 |
||